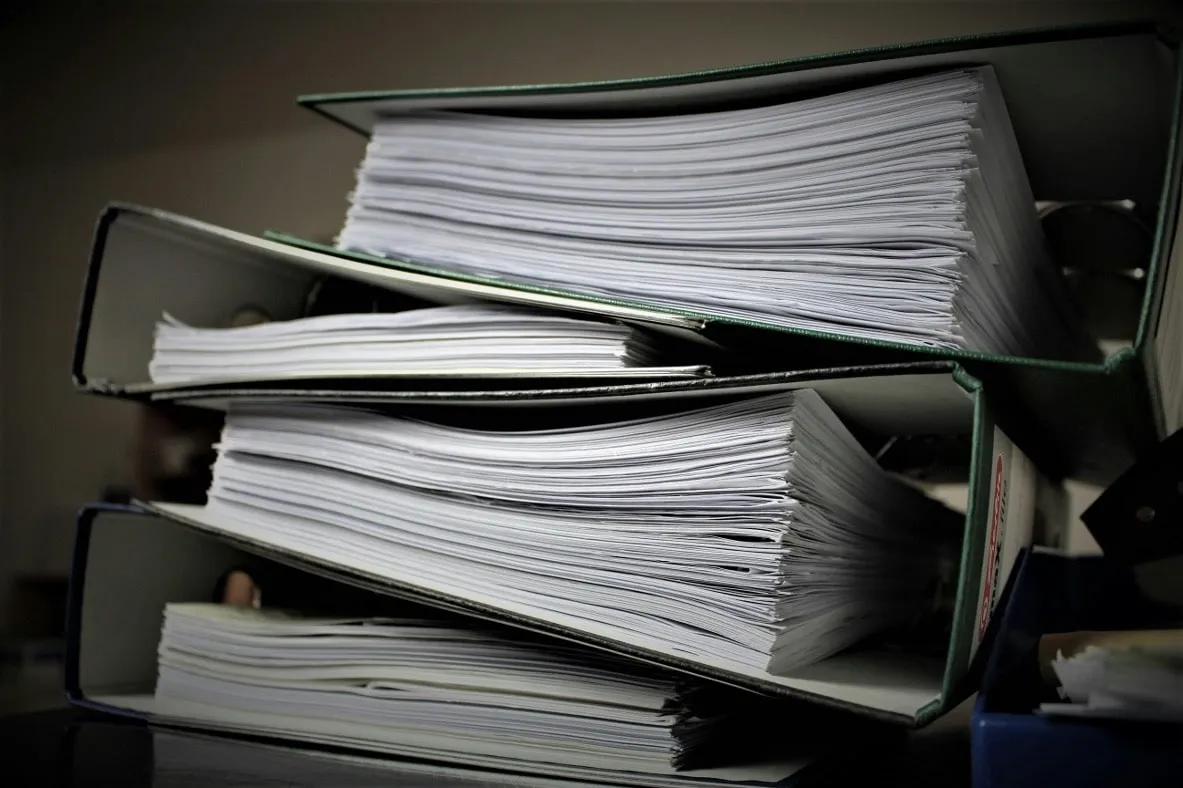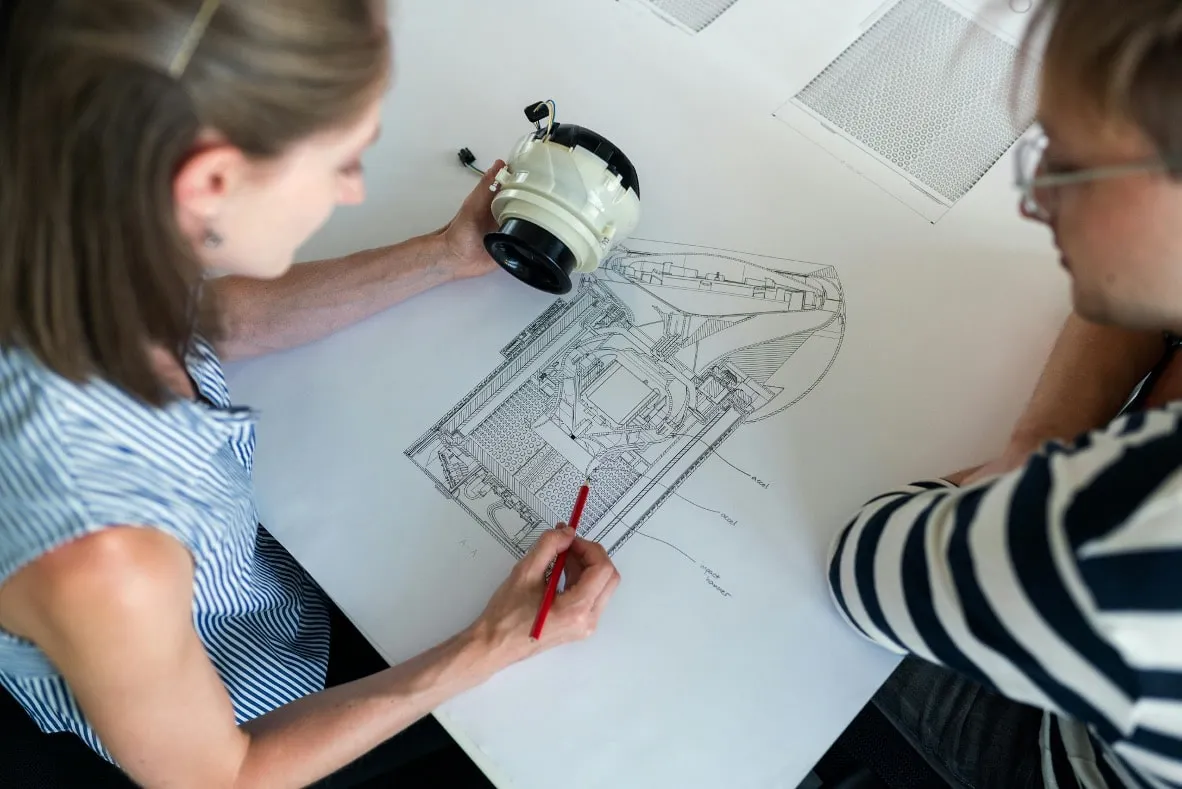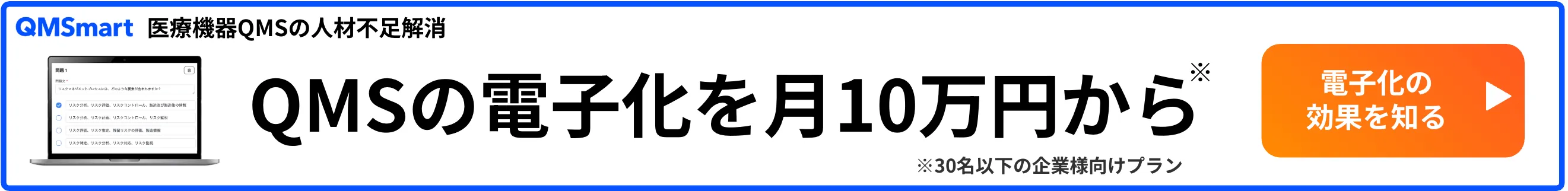ISO13485の概要と医療機器QMSにおける位置づけ
ISO13485は、医療機器の品質マネジメントシステム(QMS)に関する国際規格です。この規格は、医療機器の設計・開発、製造、保管、流通、据付け、サービス提供など、医療機器のライフサイクルにかかわる活動を行う組織が、一貫して安全で有効な医療機器を提供するために必要な品質システム要求事項を規定しています。
医療機器業界では、製品の安全性と有効性が人命に直結するため、厳格な品質管理が求められます。ISO13485は、このような医療機器特有の要求事項を考慮した規格として、世界各国の規制当局から認められており、医療機器の国際取引における共通言語としての役割も果たしています。
日本では、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法、通称:薬機法)」に基づく「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(QMS省令)」が、ISO13485を基盤として制定されています。
QMS省令は、ISO13485に日本独自の追加要求事項が加えられた内容となっており、基本的にQMS省令へ適合していれば、ISO13485の要件は満たしていると考えられます。
医療機器QMSの国際的な枠組み
医療機器の品質管理に関する国際的な枠組みとして、以下のような連携があります:
- IMDRF(International Medical Device Regulators Forum:国際医療機器規制当局フォーラム)が国際的な医療機器規制の調和を推進
- ISO13485が国際的な医療機器QMSの基準として広く採用
- 各国規制当局が、ISO13485を基礎として、自国の医療機器規制を整備
こうした国際的な調和の取り組みにより、医療機器メーカーは異なる国の市場に製品を供給する際の規制対応の負担軽減が図られています。
ISO13485の歴史と2016年版の特徴
規格の発展と改訂の歴史
ISO13485の変遷を理解することは、現行規格の要求事項の背景を把握する上で重要です:
- 1996年: ISO13485:1996として初版発行(ISO9001:1994をベースに医療機器特有の要求事項を追加)
- 2003年: ISO13485:2003として改訂(ISO9001:2000との整合性を考慮しつつ、医療機器固有の要件を強化)
- 2016年: ISO13485:2016として最新改訂(ISO9001:2008との整合性、およびISO9001:2015の改訂内容を考慮し、リスクアプローチの強化、サプライチェーン管理の拡充など)
ISO13485:2016の主な特徴
現行のISO13485:2016版は、前版から約13年ぶりの大幅な改訂となりました。主な特徴として:
- リスクアプローチの拡大: QMSのすべての側面にリスク管理の概念を適用
- バリデーション要求の強化: 特にソフトウェアバリデーションやプロセスバリデーションの要求が詳細化
- サプライチェーン管理の強化: 購買管理、外部委託プロセスの管理が拡充
- フィードバックシステムの強化: 市販後の情報収集、苦情処理と是正・予防措置への活用を強化
- ISO9001:2015との相違点: ISO9001が採用した高水準構造(HLS)を採用せず、医療機器業界の従来の構造を維持
日本では2018年3月にJIS Q 13485:2018として発行され、QMS省令との整合性が考慮されています。
ISO9001との関係
ISO13485はISO9001をベースにしていますが、以下の点で重要な違いがあります:
- ISO13485は規制目的のための要求事項に焦点を当てている
- 継続的改善よりも規制要求事項への適合と品質システムの有効性維持を重視
- 医療機器固有の要求事項(滅菌、クリーンルーム、トレーサビリティなど)を規定
- 顧客満足に加えて、患者安全を最優先事項としている
これらの違いを理解することは、ISO9001認証を取得している企業がISO13485に対応する際に特に重要です。