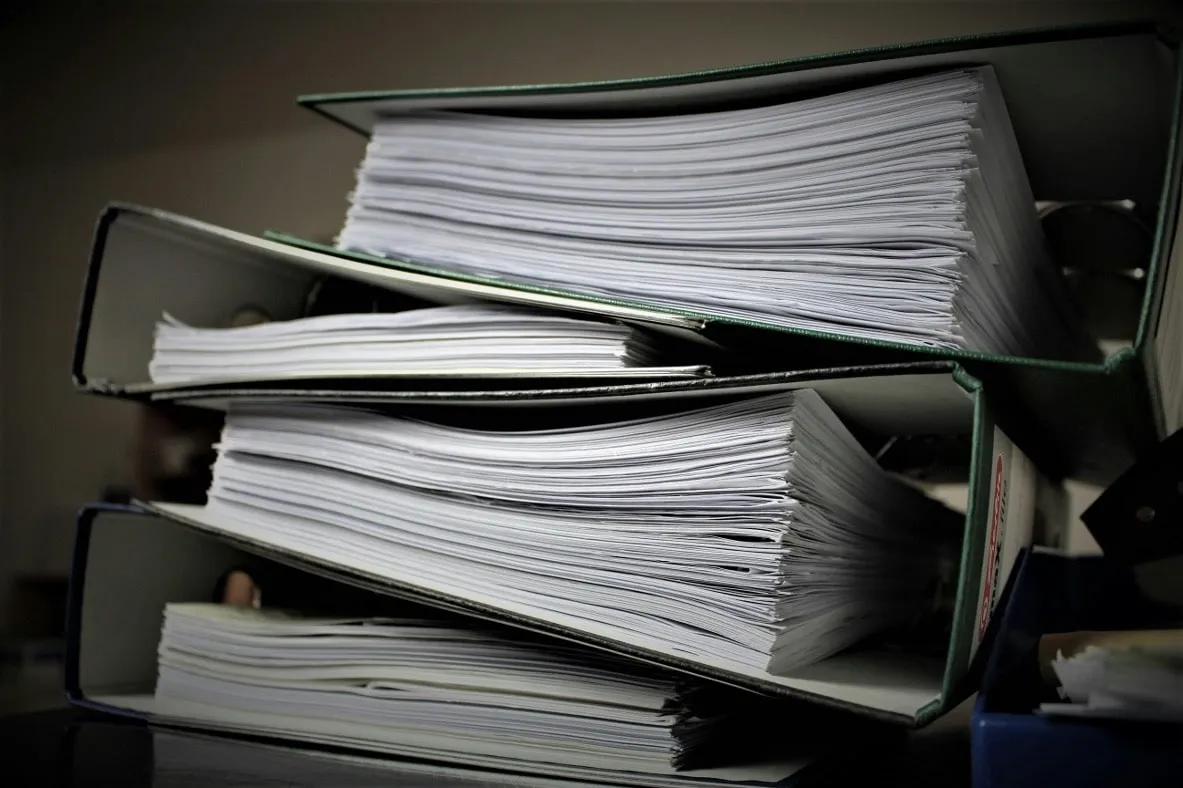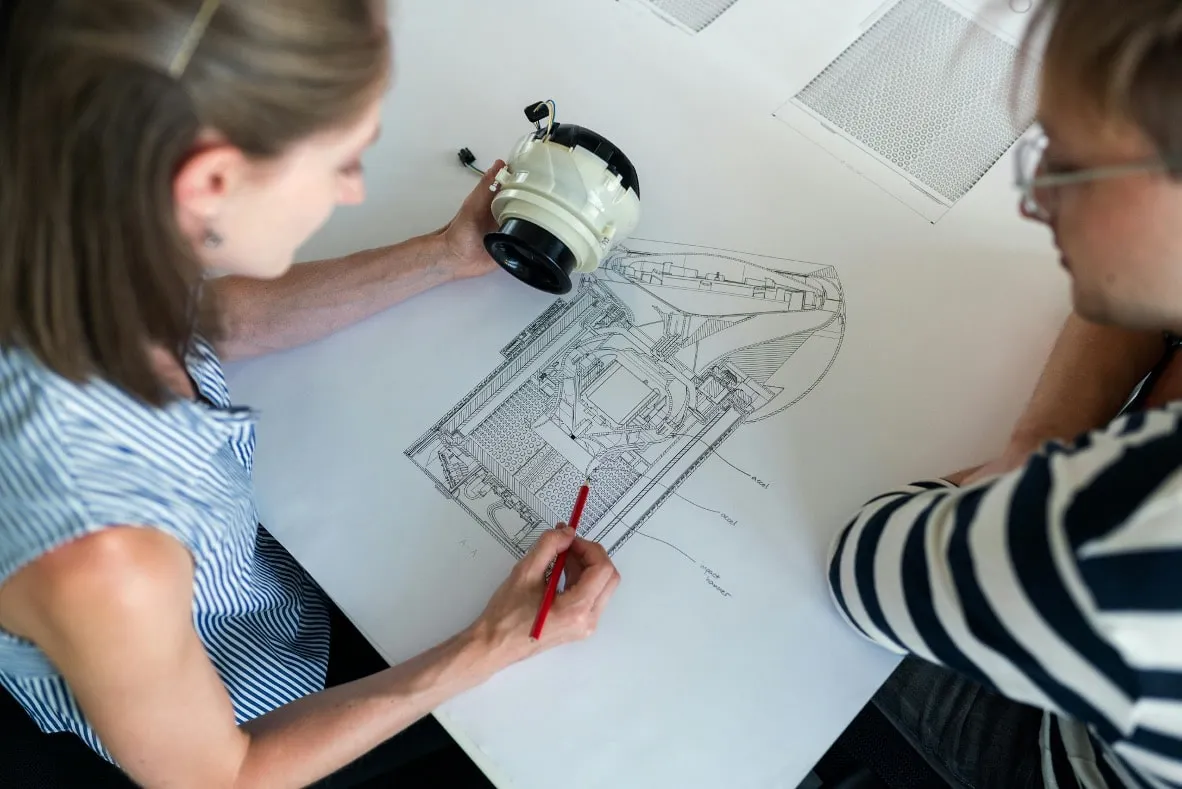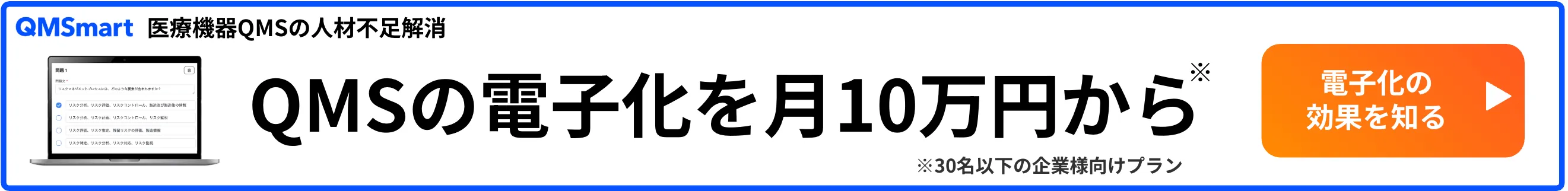はじめに
医療機器のISO13485審査(QMS調査)において、数多くの企業の審査に携わってきた経験から、指摘が多い項目Top 10とその対策についてお話しします。19年間の主任審査員としての経験を通じて、特に指摘が多かった項目に焦点を当て、実践的な改善のポイントをご紹介します。
指摘が多かった項目及び指摘内容は、あくまでも筆者の審査経験からということを、ことわっておきます。
No.1:「ISO 13485/7.6 監視機器及び測定機器の管理」(QMS 省令53条 設備及び器具の管理)に対する指摘とその対策
指摘が最も多かったのは、「ISO 13485/7.6 監視機器及び測定機器の管理」(QMS 省令53条 設備及び器具の管理)です。なぜ多いかの理由ですが、比較的不適合の状況が分かり易いというのが、主な理由かも知れません。
指摘事項の具体例
では、本項目7.6で、どういった指摘(逸脱、不適合)があったか(1)~(6)に、列記します。
(1) 検査用ソフトのバリデーション未実施
医療機器製品又は部品の監視測定(検査)にソフトウェアを使用していましたが、そのソフトウェアバリデーションを行っていませんでした。検査用治具などを使用して製品検査又は基板検査を行い、自動でOK/NGを判定するケースですが、規格で要求されているバリデーションの実施及びその記録を維持していないために、指摘となった例です。
(2) 実測値と乖離した範囲での校正実施
測定器の校正はされていましたが、製品検査で測定する値とかけ離れた値で校正されていたケースです。例えば、ある医療機器製造に関係する部品の重量測定では3gの測定を実施してしたにもかかわらず、校正は100g、200gで実施されており、3gの重量測定に対する測定値の妥当性が保証されていないために指摘となった例です。
(3) 許容誤差超過品を合格と誤判定
測定器が社内で規定された校正基準を満たしていませんでした。校正許容誤差;基準温度計との差が ±1℃以内 と規定されていながら、校正記録によれば、基準温度計との差が1.2℃(ある温度計記録;T1、基準器T2、T1-T2=1.2℃)で合格としていました。
(4) 校正手順で定めた測定点の一部省略
測定器が社内で規定された校正手順どおりに校正が実施されていませんでした。例;デジタルマイクロメーターの点検手順では、全長が25mmのデジタルマイクロメーターにおいて、測定位置は10mmと25mmを測定すると規定されています。しかしながら校正では25mmだけが測定されていました。
(5) 校正期間の超過
測定器の校正期間がオーバーしていました。2年毎に社外にて校正すると規定されていましたが、審査時点では、2年を大幅に超過していました。
(6) 測定器の誤差が製品規格を超過
製品の検査合格基準の許容範囲(公差)よりも、測定器の許容誤差が広くなっていたケース。例えば、検査の規格(基板電圧検査)が、5.0V±2%の規格(許容基準)に対し、その検査測定に使用する測定器の許容誤差は±10%とされていました。
(7) 測定器管理の基本手順の欠落
特殊な例として、レンタル会社から校正済みの測定器を使用するので、監視機器及び測定機器の管理に関する手順書を作成していなかった例、校正記録が維持されていない例、設計開発検証用の測定器が校正されていなかった例、校正対象外の測定器の識別がされていなかった指摘例などがあります。
逸脱(不適合)原因とその対策
(1) 検査用ソフトのバリデーション未実施
原因は、測定器は校正の対象という認識があるが、検査に用いるソフトウェアのバリデーションの認識がなかったこと。また正確にOK/NGの判定をできることを確認したが、そのバリデーション記録を残していなかったことです。
対策としては、ISO 13485/ 7.6の要求には測定器の校正だけでなく、検査機器にソフトウェア(プログラム)を組み込んでいる場合、そのバリデーションも要求事項であることを認識すること、ソフトウェア作成後正しく動作することを確認するだけでなく、その記録(バリデーション方法、その結果)を取っておくことです。
(2) 実測値と乖離した範囲での校正実施
原因は、単に保有している標準分銅で校正を実施していたなどです。対策としては、測定している値(レベル)を意識して、その測定値付近での校正が実施されているか、確認することです。
(3) 許容誤差超過品を合格と誤判定
原因は、校正者と確認者が同一、校正チェックシートに基準を明記していなかった又は測定値記録だけで、その基準器との差異を記入/記録するようになっていなかったなどです。対策として、基準値との差異を明記し、測定器の許容誤差との差異を比較できるようにしておくこと、実施者と確認者を別にすることなどが考えられます。
(4) 校正手順で定めた測定点の一部省略
原因は、測定機器管理規定の周知不足、理解不足などが考えられます。対策としては、校正記録様式に規定のポイントなる事項を転記しておくことなどが考えられます。または規定に沿った校正記録記入表にしておくことなどが考えられます。
(5) 校正期間の大幅超過
原因は、測定器の管理不足です。1台しかないため校正に出すと生産がストップしてしまう状況でした。この場合の対策としては、予備用の測定器を購入する、校正に出している期間は測定器をレンタルする等が考えられます。
もう一つの原因は、測定器の期限管理がきちんとされていなかった事などが考えられます。この場合は、Microsoft Excel表などで、毎月に期限がくる測定器を表示するなりして、分かり易くすること、または、社内の測定器の校正時期(半年に1回、年に1回など)を揃えるなどが考えられます。
(6) 測定器の誤差が製品規格を超過
原因は、電圧計、電流計など測定器の許容誤差が一律に設定されていたことなどがあげられます。対策としては、製品の検査結果の合否判定基準の幅(公差%)と比較して、測定器の校正の許容誤差(%)を十分小さくすることが求められます。
重要なポイント
ISO 13485/7.6の冒頭の要求文は、下記です。
「規定した要求事項に対する製品の適合性を実証するために,組織は,実施する監視及び測定を明確にする。また,そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にする。
組織は,監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できること,及び実施することを確実にする手順を文書化する。」
これをブレークダウンして箇条書きにすると、以下となり、この7.6の目的がはっきりしてきます。
- 製品の適合性を実証するために,組織は,実施する監視及び測定を明確にする。
- そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にする。
- 監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できること。
測定器の校正は、一律的又は機械的に実施するのではなく、測定器管理の目的をよく考えての管理が求められます。
ISO 13485/7.6の要求文 「規定した要求事項に対する製品の適合性を実証するために,組織は,実施する監視及び測定を明確にする。」にあるように、目的は、要求の下線部にあります。言い換えると、その医療機器の監視、測定において、医療機器製品に求められる「規定した要求事項」すなわち製品の合否判定基準を満たしているかを実証するためです。
もう一つのポイントは、ISO 13485/7.6の要求文 「組織は,監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できること,及び実施することを確実にする。」の下線部にあるように、「ISO 13485/ 8.2.6 製品の監視及び測定」で求められる内容と、監視機器及び測定器の管理が整合しているかがポイントです。
審査における指摘(逸脱、不適合)の例は、これら目的を忘れているか、意識していないこと、さらに「ISO 13485/ 8.2.6製品の監視及び測定」で求められる内容と、監視機器及び測定器の管理が整合していることの確認を怠った結果と言えるでしょう。
No.2:「ISO 13485/8.5.2 是正処置」(QMS 省令63条 是正措置)に対する指摘とその対策
是正処置は、主に顧客苦情が自社製品の設計または製造で原因があった場合に取られる処置で、品質マネジメントシステムでは重要な位置を占めるため、ISO 13485では、多くの要求事項が規定されています。PDCAサイクルでは、Aに該当します。
指摘事項の具体例
(1) 是正処置の悪影響検証が未実施・未記録
この是正処置の項目で一番多い指摘は、8.5.2 e)の要求 「是正処置が,適用される規制要求事項へ適合するための能力又は医療機器の安全性及び性能への悪影響を与えていないことの検証」 に対する逸脱(不適合)です。悪影響を検証していないか、または検証したとしても、その検証結果を記録していないケースです。
(2) 是正処置の有効性レビューの未実施または未記録
この是正処置の項目で次に多いのが、8.5.2 f) の要求「とった是正処置の有効性のレビュー」に対する逸脱(不適合)です。有効性のレビューを実施していないか、その記録をしていないケースです。
(3) 是正処置実施の記録未維持
「ISO 13485/ 8.5.2是正処置」の要求の最後の行に記載の「全ての調査及びとった処置の結果の記録は,維持する」に対する指摘もあります。すなわち、是正処置を取っていながら、是正処置記録を取っていないケースです。
(4) 是正処置に伴う関連文書の更新漏れ
是正処置の項目8.5.2 d) 「必要な処置の計画及び文書化,並びにその処置の実施。適切な場合,文書の更新を含む」に対する指摘もあります。例えば設計変更などの是正処置を取った結果、関連文書・作業手順書などの更新も必要になった場合に、その作業手順書の更新について明記されていなかったケースです。
逸脱(不適合)原因とその対策
(1) 是正処置の悪影響検証が未実施・未記録
原因;ISO 13485:2016年版で新たに追加された項目のためという理由が多い。品質マニュアルには反映したが、その下位文書「是正処置要領」または「是正処置手順書」に反映されていなかったのが原因だったケース、さらに是正処置報告書の様式の改訂もれだったのが原因でした。
対策;上記原因から分かるように、品質マニュアル、下位文書「是正処置要領」または「是正処置手順書」への反映、さらには、是正処置報告書の改訂などです。
(2)是正処置の有効性レビューの未実施または未記録
原因;一口で言えば、「是正処置要領」または「是正処置手順書」の理解が不十分だったのが、原因としてあげられます。この要求の意図は、取った是正処置が有効に機能しているか、再発していないかを確認することを意味しています。したがって、是正処置を取った後に一定期間モニタリングするか、一定期間後に検証/確認することが、通常必要です。
対策;この項目の目的・意味を深く理解することです。
(3)是正処置実施の記録未維持
原因;この原因は、組織にとって比較的大きな問題が発生した場合、例えば、医療機器の回収が必要になったケース、設計上の大問題が発生したケースに生じやすい逸脱です。医療機器の回収で規定当局への届出、回収の実施は行っているが、是正処置の記録が残っていないことがあります。また設計上の大問題で設計変更も適切に実施され、市場で稼働している医療機器に対する対策も完璧に行われているにも関わらず、是正処置報告書が記録、維持されていない場合があります。社内のほとんどの関係者が知っているためなどで、是正処置報告書の必要性を感じなかったのが、原因かも知れません。
対策;「是正処置手順書」または「苦情処理手順書」などには、本要求が、規定されていると考えられるので、その再教育を実施することなどが考えられる。また苦情一覧表、不適合一覧表などで、回収や設計上の大問題も含めて、そのような管理表で管理し、是正処置の発行の有無を管理していくことが有効でしょう。
(4)是正処置に伴う関連文書の更新漏れ
原因;是正処置を取った時点で、取られた是正処置に関連する文書類を検討、考慮しなかったのが、原因と考えられます。また是正処置報告書の様式が、そこまで考慮しなかったのも原因と考えられます。
対策;この項目8.5.2 d)の目的、意味を伝えた再教育及び是正処置報告書の改善が考えられます。
重要なポイント
この「ISO 13485/8.5.2 是正処置」に対する要求は、a)~f)とはっきりしているので、是正処置要求書の様式を充実することが、有効と考えられます。また単にa)からf)の項目欄を設けるだけでなく、その解説や意味などを注記する、更に、ベスト記載事例を、準備することなどが有効な対策として、考えられます。
是正処置報告書の記載そのものの漏れ防止としては、「フィードバック」、「苦情処置」または「内部監査」などから是正処置が必要と判断されたら、是正処置管理一覧表などを作成して、その一覧表により是正処置報告書の発行実績を維持管理することが有効でしょう。
No.3:「ISO 13485/7.1 製品実現・リスクマネジメント」(QMS 省令63条 製品実現・リスクマネジメント)に対する指摘とその対策
指摘事項の例
(1) 製造・製造後活動への不適合
このリスクマネジメントにおいて、圧倒的に多い指摘は、JIS T 14971:2020の第10項「製造及び製造後の活動」に対する不適合です。
(2) リスクマネジメントの未実施または記録欠落
上記の指摘が大部分を占めますが、リスクマネジメントを実施していない、または記録を残していないなどの指摘も時折見られます。
(3) リスクマネジメント計画の文書化不備
頻度は多くありませんが、JIS T 14971:2020の第4.4項に規定されるリスクマネジメント計画が文書化されていないケースが時折確認されています。
(4) リスクマネジメント報告書の名称誤用
指摘事項とはならない改善の機会レベルですが、「リスクマネジメント報告書」という名称の誤用が見られます。
(5) リスク分析での危害の記載漏れ
リスク分析の記録において、危害が明記されていないケースが時折確認されています。
逸脱(不適合)原因とその対策
(1) 製造・製造後活動への不適合
JIS T 14971:2020の「第10項 製造及び製造後の活動」に対する不適合の主な原因は、次のような事が考えられます。医療機器の製造販売認証申請では、その申請書類(添付資料)に、リスクマネジメントの記載が必須ですので、設計開発プロセスでは、きちんと第9項までは実施するが、いったん医療機器製造販売認証を取得してしまうと、「第10項 製造及び製造後の活動」がリスクマネジメントの要求であることを忘れるか、軽視しているように感じられます。また製造及び製造後に安全性に関する事象が発生していないから記録を残していないという組織もあります。製造及び製造後に安全性に関する事象が発生していない場合は、第10項 製造及び製造後の活動を実施した証として、フィードバック又は苦情処理をある期間(例えば1年)レビューして、「安全性に関する事象はなかった、新たなリスクは発生していなかった」などという記録を残すことが必要です。これをいつ実施するかですが、忘れないようにするために、マネジメントレビューのタイミングで実施し、そこで、マネジメントレビューのインプットの記録として、維持することを推奨します。
(2) リスクマネジメントの未実施または記録欠落
リスクマネジメントを実施していない組織は、「設計工程」及び「主たる組立て」の工程を担当していない輸入業者などにみられる特徴です。申請時には、その組織の認証申請担当(例えば 薬事部門)海外製造所のリスクマネジメント情報を申請時の添付資料に記入することで済ませ、自社の現場部門(技術、営業技術)では、ほとんど実施していないというのが実態のようです。
(3) リスクマネジメント計画の文書化不備
リスクマネジメント計画の文書化されていない原因として、JIS T 14971:2020の図1-リスクマネジメントプロセスの概略図をみても「リスク分析」のステップから開始されているのも影響しているかも知れません。JIS T 14971:2020の第4.4項 リスクマネジメント計画のほとんどは、設計開発する医療機器が類似(同一製品群または同一一般的名称)であれば、変わる事は少ないと考えられるので、手順書に含めることも問題ないと考えられます。個々の医療機器の設計開発プロセスの開始時には、第4.4項 b)の「責任及び権限の割当て」対してのみに注意して、その段階で、リスクマネジメントの「責任及び権限」を記録に残しておけばいいでしょう。
(4) リスクマネジメント報告書の名称誤用
記録名称・「リスクマネジメント報告書」は、JIS T 14971:2020の第9項のリスクマネジメントのレビューの結果の記録をいいます。リスクマネジメントの設計開発プロセス時のリスク分析からリスクマネジメントレビューまでの記録は、リスクマネジメントとファイルといいます。(製造後は、製造及び製造後の情報も含みます。) リスク分析から全体的な残留リスクまでの記録を「リスクマネジメント報告書」と称している組織がたまに見受けられますが、JIS T 14971:2020の定義から言えば、逸脱しています。
(5) リスク分析での危害の記載漏れ
JIS T 14971:2020での危害は、第3.3項で「人の受ける傷害若しくは健康障害.又は財産若しくは環境の受ける害」と定義されています。したがってなんらかの予想される患者の健康被害を記載する必要があります。たまに「危険状態」の記述にとどまっている事例が見受けられます。(JIS T 14971:2020附属書C参照)
重要なポイント
まずは、審査時に指摘を受けないために、JIS T 14971:2020の「第10項 製造及び製造後の活動」に対する記録を残す仕組みをしっかり作っておくことです。
リスクマネジメントを医療機器製造販売認証申請のため、またはISO 13485の審査で指摘を受けないためという目的にだけ実施しているとしたら、それは本来の目的から逸脱しています。
製造販売業として、製造販売している医療機器が市販後に患者又は使用者に対して健康被害を極力防ぐために細心の注意でリスクマネジメントを実施するというのが、本来の目的です。
ある組織の経営者が、医療機器を製造販売するにあたって、「自分、自分の家族または肉親が患者になって使用する場合を想定して、医療機器の製造販売にあたっている。」という言葉が印象に残っています。リスクマネジメント実施する担当者は対象医療器のリスクマネジメントを実施するにあたって、自分、自分の家族または肉親が、患者になった場合を想定して進める事が実効性を上げるのでないかと思っています。
PMDAのWebサイト・回収情報(医療機器)によれば、(2024年1月5日現在で)、2024年の回収件数は、クラスⅠは0件、クラスⅡは、番号2-11672~2-12141(ただし欠番あり)で、欠番を考慮せずに単純計算すると470件、クラスⅢは、番号3-2902~3-2956(ただし欠番あり)で、欠番を考慮せずに単純計算すると55件あった。
(注記)
クラスⅠ;その製品の使用等が、重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る状況
クラスⅡ;その製品の使用等が、一時的な若しくは医学的に治癒可能な健康被害の原因となる可能性がある状況又はその製品の使用等による重篤な健康被害のおそれはまず考えられない状況
クラスⅢ; その製品の使用等が、健康被害の原因となるとはまず考えられない状況
PMDAのWebサイト「不具合が疑われる症例報告に関する情報」で、例として一般的名称「移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置」で検索してみると、2009年~2023年で24件あった。
また医療機器センターの「不具合DB」で報告年月日R6/3、大分類 「1 画像診断用機器」で検索すると16件あった。
リスクマネジメントをより慎重に実施した場合に、これら回収または不具合を未然に防げたかどうかは、当事者のみが知るところでしょう。しかしながら当事者は、次回の医療機器の設計開発プロセスのリスクマネジメントにおいてこれらの事象(不具合また回収)を重視することでしょう。
さらに当事者でなくても、これら安全情報を監視し、常に自社のリスクマネジメントに活かすことでより市場での患者へのリスクを低減し、未然に不具合、回収を防げるのではないでしょうか。
以上

-min.webp)