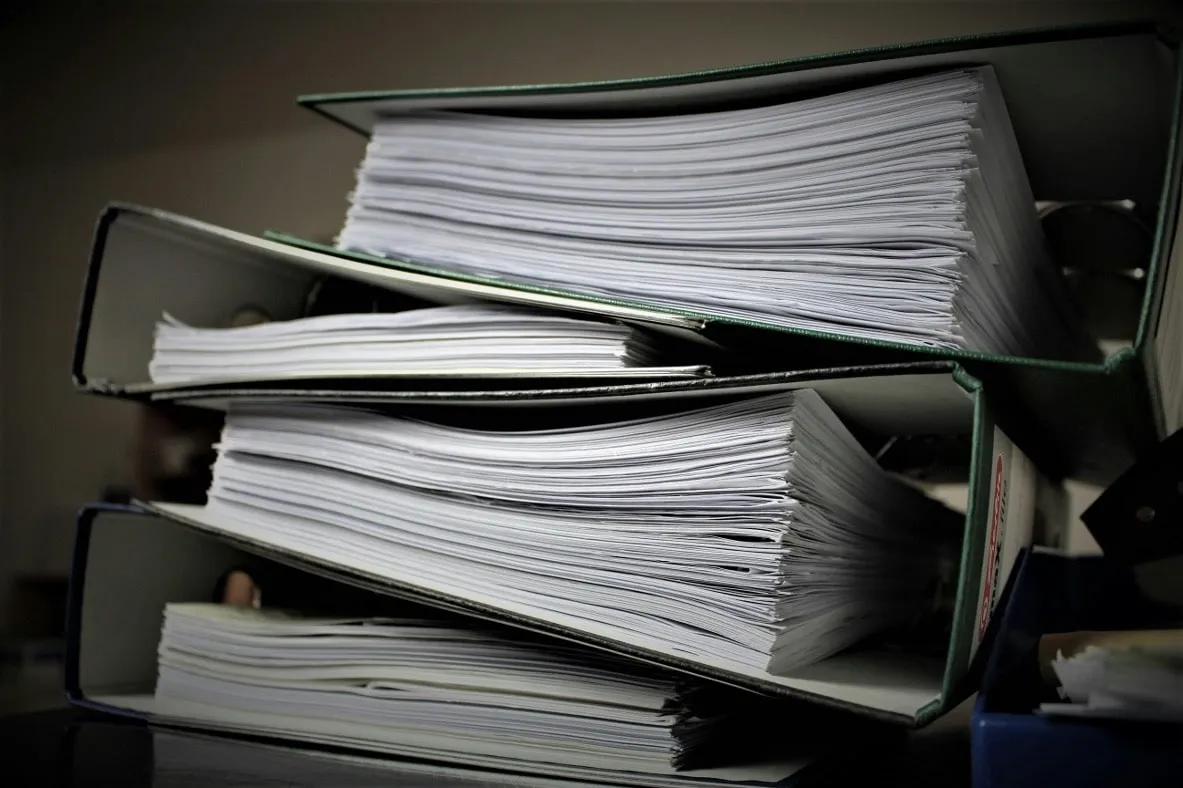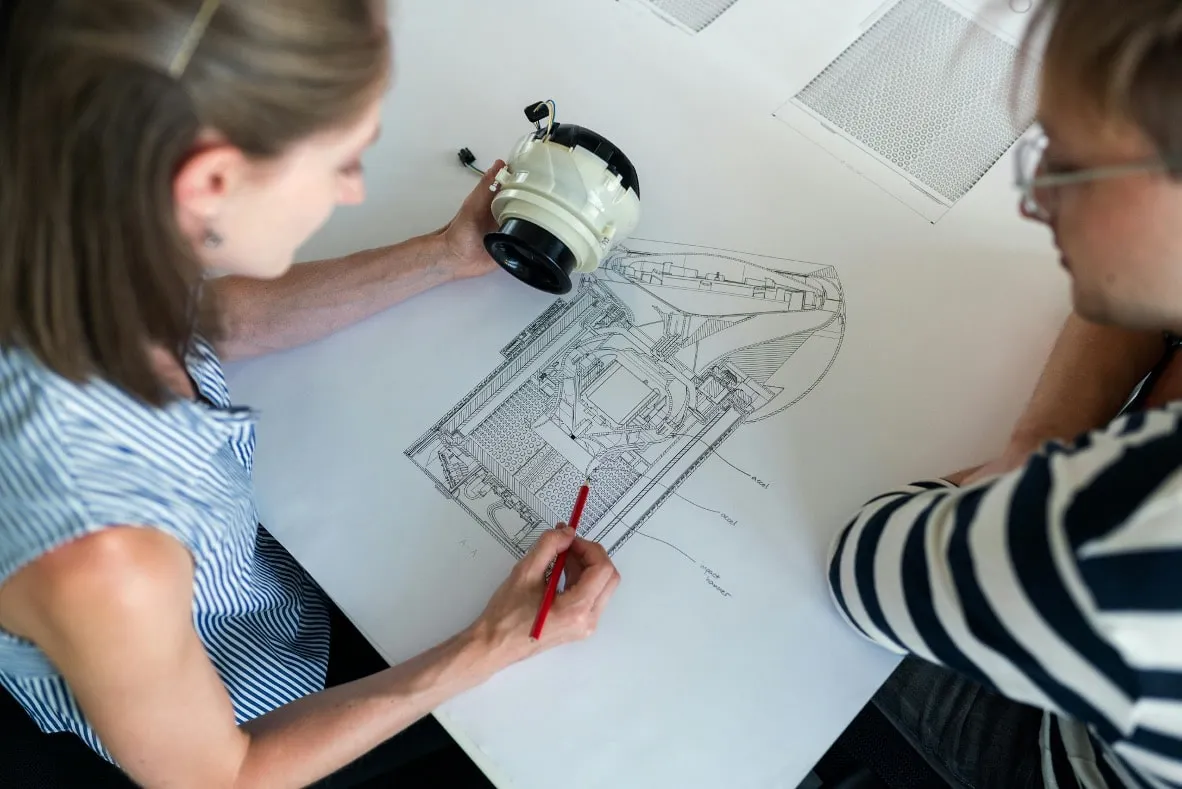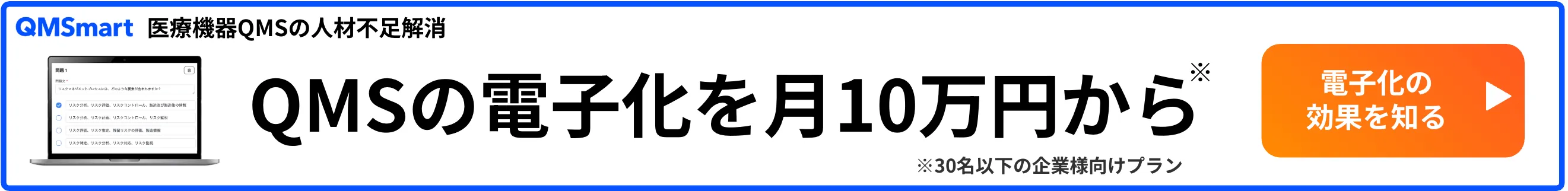測定機器の校正管理とは?
測定機器の校正管理は、医療機器のQMS(品質管理監督システム)において重要な役割を果たします。この管理プロセスは、製造や検査に使用される測定機器の精度と信頼性を確保することを目的としています。具体的には、測定機器が正確な値を示し続けるよう、定期的に表示値の確からしさの確認を行い、その結果を記録・管理することを指します。
測定機器の校正管理は、医療機器の品質を保証する上で欠かせない要素です。例えば、血圧計の製造過程を想像してみてください。もし使用する測定機器が正確でなければ、製品の安全性、有効性にも影響を及ぼし、患者の健康に直接的な悪影響を与える可能性があります。これは、料理人が目盛りのないカップを使用して重要な材料を測る状況に似ています。結果として、料理の味や質が一定に保てなくなるのと同じです。
医療機器業界において、測定機器の校正管理は単なる品質管理の一部ではなく、法的要求事項でもあります。多くの国で、医療機器製造業者に対して、QMSの一環として厳格な校正管理を求めています。これにより、製品の安全性と有効性が担保され、患者や医療従事者の信頼を得ることができるのです。
測定機器の校正管理は、使用する機器の種類や用途に応じて、適切な頻度と方法で実施する必要があります。ほとんど狂う心配がないステンレス製の定規からちょっとした振動で影響が出る電子天秤まで様々です。また、目視で読み取れる精度で十分な場合と目視では判断できない精度が必要な場合も存在します。従いまして、機器の特性と使用目的を考慮した校正の頻度と方法を定める必要があります。
また、校正管理には、国際標準や国内規制に基づいた手順の確立、トレーサビリティの確保、そして結果の文書化も含まれます。適切な校正管理により、製品の品質向上だけでなく、製造プロセスの効率化や、不適合品の削減にもつながります。
さらに、校正で不合格となった場合の製品の安全性、有効性を確認したうえで出荷することも重要です。QMSでは、不合格となった測定機器で計測を行った製品への影響を調査したうえで、出荷可否判定を行うことを要求しています。
測定機器の校正管理の必要性
測定機器の校正管理プロセスを導入することで、製品の信頼性向上から法令遵守まで、多岐にわたるメリットが得られます。以下、その必要性と具体的な利点について詳しく説明します。
まず、測定機器の校正管理の最大のメリットは**、製品品質の一貫性と信頼性の確保**です。適切に校正された機器を使用することで、製造工程や最終検査における測定値の信頼性が高まります。これは、例えば人工呼吸器の流量制御や、インプラント製品の寸法精度など、患者の生命に直結する要素の品質保証に直接寄与します。
次に、法令遵守の観点からも校正管理は不可欠です。日本では薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づくQMS省令において、測定機器の管理が明確に要求されています。同様に、欧州のMDR(Medical Device Regulation)や米国のQSR(Quality System Regulation)の規制においても、測定機器の校正は重要な要素として位置付けられています。
さらに、校正管理は製造プロセスの効率化にも貢献します。正確な測定により、製造パラメータの最適化が可能になり、不良品の発生率を低減できます。これは材料やエネルギーの無駄を減らし、コスト削減にもつながります。
また、校正管理は問題発生時のトレーサビリティ確保にも役立ちます。製品に問題が発見された場合、使用された測定機器の校正記録を追跡することで、問題の原因特定や影響範囲の把握が容易になります。これにより、迅速かつ的確な是正措置が可能となり、患者への影響を最小限に抑えることができます。
最後に、適切な校正管理は企業の信頼性向上にも寄与します。厳格な品質管理体制の証として、顧客や規制当局からの信頼獲得につながります。これは新規市場への参入や、競争力の強化にもつながる重要な要素となります。
以上のように、測定機器の校正管理は、製品品質、法令遵守、効率化、トレーサビリティ、そして企業信頼性など、多岐にわたる領域で重要な役割を果たします。医療機器産業において、この管理プロセスの重要性はますます高まっていると言えるでしょう。
%20(1)-min.webp)