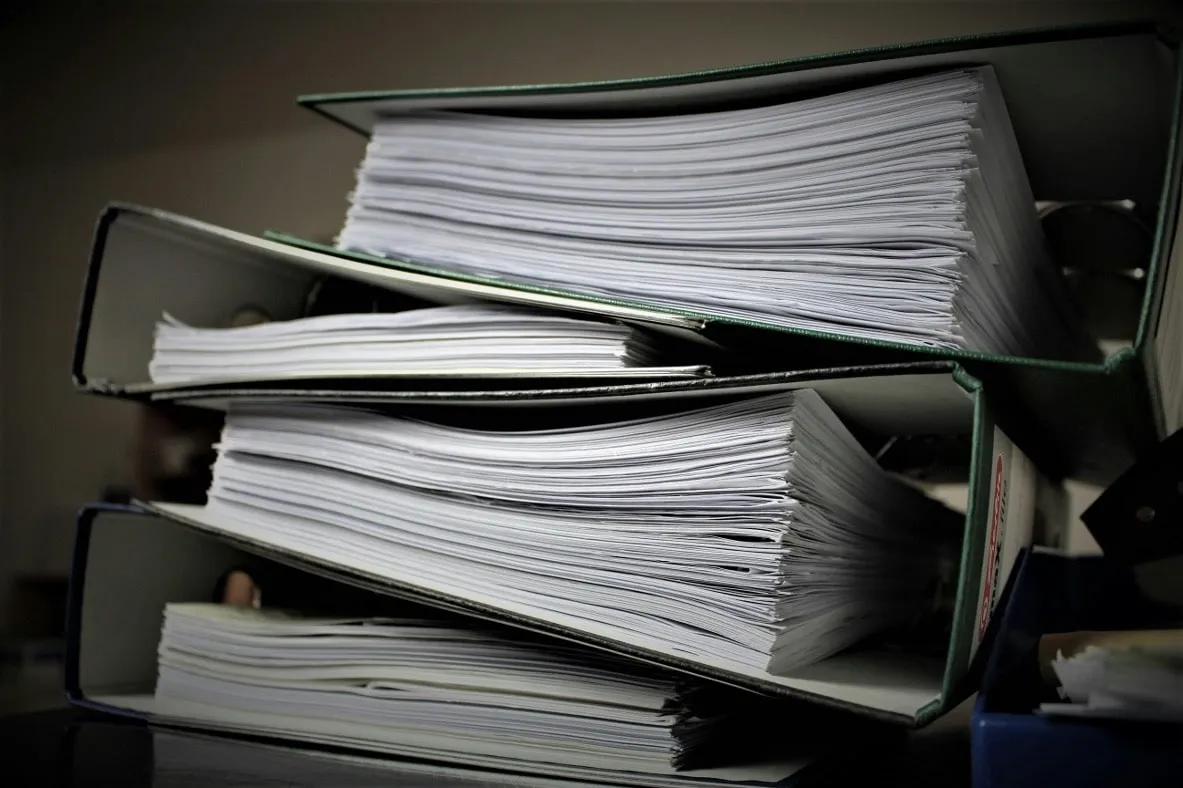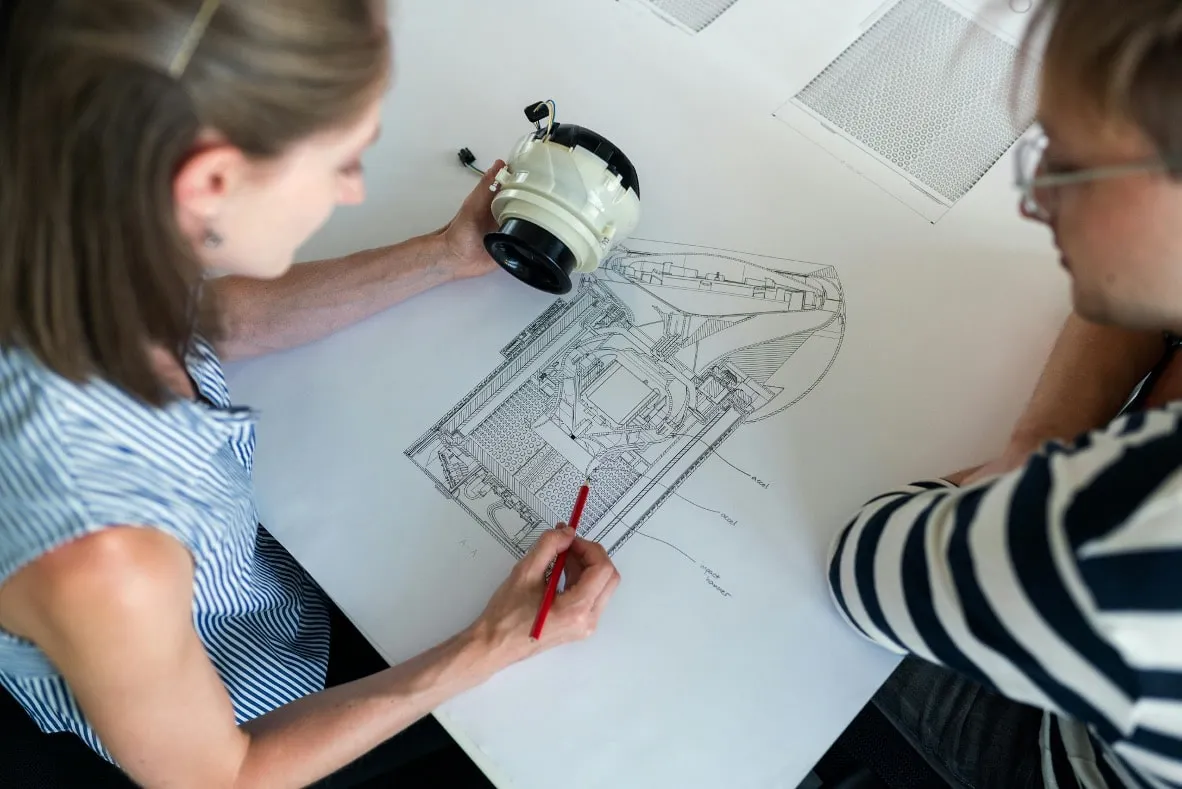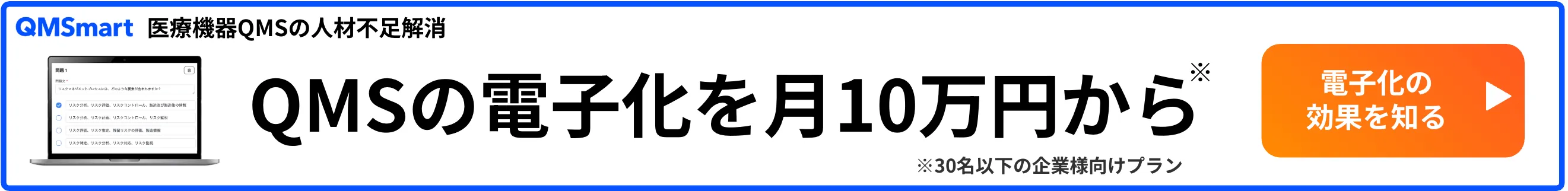プロセスバリデーションの基礎と重要性
医療機器の製造において、品質は患者の安全に直結する重要な要素です。この品質を確保するための重要な手法の一つが「プロセスバリデーション」です。QMS省令(医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令)第45条では、プロセスバリデーションを「実施した製品の製造及びサービスの提供に係る工程について、それ以降の監視若しくは測定では当該工程の結果たる工程出力情報を検証することができない場合、当該工程について、バリデーションを行わなければならない」と規定しています。
簡潔に言えば、プロセスバリデーションとは「製造プロセスが一貫して要求される品質の製品を生産する能力があることを、事前に検証・文書化すること」です。通常の検査や測定だけでは製品の品質を保証できないプロセスに対して実施する必要があります。
医療機器製造におけるプロセスバリデーションの重要性は以下のポイントに集約されます:
- 患者安全の確保: 不適切なプロセスは不良品を生み出し、最終的に患者のリスクとなります
- 規制要件への適合: 世界各国の医療機器規制はプロセスバリデーションを要求しています
- 製品品質の一貫性確保: バリデーション済みプロセスは品質のばらつきを最小化します
- コスト削減: 不適合品の低減によるコスト削減につながります
- リコールリスクの低減: 適切にバリデーションされたプロセスは市場での不具合発生率を下げます
プロセスバリデーションが特に重要となるのは、検査だけでは品質を完全に検証できない、もしくは検査で品質を検証することが現実的でない「特殊工程」と呼ばれるプロセスです。例えば、滅菌工程、接着工程、溶接工程、成形工程などが該当します。
法的要件と規制背景
QMS省令におけるプロセスバリデーションの要求事項
QMS省令(平成16年厚生労働省令第169号)では、主に以下の条項でプロセスバリデーションに関する要求事項が規定されています:
- 第45条(製造工程等のバリデーション):一般的なプロセスバリデーションの要求事項
- 第46条(滅菌工程及び無菌バリアシステムに係る工程のバリデーション):滅菌および無菌関連のバリデーション要求事項
- 第5条の6(ソフトウェアの使用):製造に使用するソフトウェアのバリデーション要求事項
特に第45条では、バリデーション対象となるプロセスの明確化、バリデーションの手順の文書化、バリデーション結果の記録・保管などが要求されています。また、再バリデーションの条件や判定基準の設定についても規定されています。
さらに、新製品の製造工程の検討は、医療機器の設計開発の一部となるため、設計開発計画に従ってプロセスの構築とバリデーションを実施する必要があります。
ISO 13485:2016の関連要求事項
国際規格であるISO 13485:2016では、7.5.6項「生産及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認」において、プロセスバリデーションに関する要求事項が規定されています。主な要求事項は以下の通りです:
- バリデーション対象プロセスの決定基準
- プロセスのレビューと承認のための基準
- 設備の適格性確認と要員の資格認定
- 設備の操作方法と手順の制定
- 記録に関する要求事項
- 統計的手法を含む妥当性確認の方法
- 再バリデーションの要求事項
- プロセス変更の承認
各国規制の特徴と相違点
主要国の規制においても、プロセスバリデーションは重要な要素として位置づけられています:
- 米国FDA QSR (21 CFR 820.75): 「Process Validation」として詳細な要求事項を規定。特に「予測的バリデーション」を重視しています。
- EU MDR (2017/745): Annex IXにおいて、製造プロセスの検証を要求。特に滅菌や無菌バリアシステムに関する厳格なバリデーションを要求しています。
- 中国NMPA: 中国医療機器GMP(医療器械生産質量管理規範)においてもプロセスバリデーションが要求されています。
グローバル展開する医療機器メーカーは、これらの地域間の微妙な要求の違いを理解し、最も厳しい要求に合わせたバリデーション体制を構築することが効率的です。
プロセスバリデーションの基本的アプローチ
バリデーション対象プロセスの特定
プロセスバリデーションの第一歩は、バリデーションが必要なプロセスを特定することです。一般的に、以下のような特性を持つプロセスがバリデーション対象となります:
- 検査や試験だけでは品質を完全に検証できないプロセス
- 検査や試験で品質を検証することが現実的でないプロセス
- プロセスの結果が製品の品質に直接影響するプロセス
- バラツキが製品品質に重大な影響を与える可能性があるプロセス
- 自動化されたプロセスや複雑なプロセス
具体的には、滅菌工程、接着工程、溶接工程、成形工程、コーティング工程、無菌充填工程などが典型的なバリデーション対象プロセスです。
バリデーションの種類
プロセスバリデーションは、実施するタイミングによって以下の3種類に分けられます:
- 予測的バリデーション(Prospective Validation): 実生産前に行うバリデーション。最も一般的かつ推奨される方法で、通常はIQ/OQ/PQのステップで実施されます。
- 同時的バリデーション(Concurrent Validation): 実生産中に行うバリデーション。既に市場に出ている製品や、生産数が限られる製品において実施されることがあります。
- 回顧的バリデーション(Retrospective Validation): 過去の生産データを分析して行うバリデーション。現在の規制環境では単独での使用は一般的に認められていませんが、予測的バリデーションの補完として活用されることがあります。
IQ/OQ/PQアプローチ
医療機器のプロセスバリデーションは、一般的にIQ/OQ/PQという3つのステップで実施されます:
1. IQ(据付時適格性確認:Installation Qualification)
製造設備が正しく据付けられ、供給元の仕様や要求事項に適合していることを検証します。主な確認項目は:
- 設備/機器の仕様(搭載されているソフトウェアの仕様を含む)確認
- 設置環境の確認(電源、水、空気等のユーティリティ)
- 設備/機器の設置状況
- 校正状態の確認
- 安全機能の確認
- 付属文書(操作マニュアル等)、付属部品の確認
2. OQ(運転時適格性確認:Operational Qualification)
製造設備が意図したとおりに動作し、設定された運転パラメータ内で正常に機能することを検証します。主な確認項目は:
- 操作手順の確認
- パラメータの上限/下限での動作確認
- アラーム/警告機能の確認
- ソフトウェア機能の確認
- 最悪条件(Worst Case)での検証
3. PQ(性能適格性確認:Performance Qualification)
製造設備が実際の生産条件下で、一貫して要求品質の製品を製造できることを検証します。製造ラインの立ち上げ時のように、複数の設備/機器のPQを実施する場合は、一貫した製造工程で実施することが必要になるます。主な確認項目は:
- 実際の生産条件下での製造
- 複数バッチ/ロットでの再現性確認
- 長期的な性能安定性の確認
- 製品品質への影響評価
- プロセスの許容範囲(Process Window)の確立
%20(2)-min.webp)
バリデーション計画書・報告書の作成ポイント
適切なバリデーション文書は、バリデーションの成功と規制遵守の鍵となります。以下に重要なポイントを示します:
バリデーション計画書(プロトコル)の主要要素:
- 目的とスコープの明確な定義
- 責任者と関与部門の明確化
- 前提条件と受入基準の設定
- 詳細なバリデーション方法と手順
- サンプルサイズとその統計的根拠
- 判定基準の明確な定義
- 逸脱時の対応手順
バリデーション報告書の主要要素:
- 計画書との対応関係の明示
- 実施日時と担当者
- 実際に使用した設備/機器、材料等の詳細な情報
- 実際のバリデーション結果の詳細な記録
- 判定基準に対する評価結果
- 逸脱があった場合の詳細と対応
- 結論と承認
各文書は、適切な権限を持つ責任者による承認が必要です。特に品質保証部門の承認は必須となります。
複数の設備・機器をバリデーションする場合や複雑な工程をバリデーションする場合は、別途バリデーションマスタープランで総括的な各設備・機器のバリデーション計画を作成することもあります。
特殊工程のバリデーション手法
医療機器製造には、特に注意が必要な特殊工程があります。これらの工程は独自のバリデーション手法が要求されます。
滅菌プロセスのバリデーション
滅菌プロセスは、医療機器の安全性に直結する重要な工程です。滅菌方法に応じて、以下の国際規格に基づくバリデーションが要求されます:
- エチレンオキサイド滅菌(EO滅菌): ISO 11135に基づくバリデーション
- 放射線滅菌: ISO 11137シリーズに基づくバリデーション
- 湿熱滅菌: ISO 17665に基づくバリデーション
- 乾熱滅菌: ISO 20857に基づくバリデーション
滅菌バリデーションでは、物理的パラメータの確認だけでなく、生物学的指標(BI)や化学的指標(CI)を用いた微生物学的検証も重要です。また、滅菌工程のバリデーションは一般的に以下のステップで実施されます:
- 製品のバイオバーデン(微生物負荷)評価
- 滅菌工程開発と定義
- 滅菌工程のバリデーション(最小・最大負荷条件での検証を含む)
- ルーチンモニタリングと管理
洗浄プロセスのバリデーション
洗浄プロセスのバリデーションは、特にアレルギー物質を含む原材料を使用した医療機器、再使用可能医療機器や生物由来物質を扱う工程で重要です。主なステップは:
- 洗浄剤と洗浄方法の選定
- 残留物の許容基準設定
- 最悪条件(汚れが最も落ちにくい条件)の特定
- 検出方法の確立
- 洗浄効果の検証
残留物の評価には、目視検査、ATP測定、TOC(全有機炭素)分析、タンパク質定量などの方法が用いられます。
接着・溶接工程のバリデーション
接着や溶接などの結合工程は、最終製品の検査だけでは品質を完全に評価できないことが多いため、バリデーションが特に重要です:
- 接着工程: 接着剤の選定、表面処理方法、硬化条件、接着強度試験、密封性試験などを含むバリデーション
- 溶接工程: 溶接パラメータ(温度、圧力、時間など)の最適化と検証
- 超音波溶着: エネルギー、時間、圧力などのパラメータ検証
これらの工程では、破壊試験と非破壊試験を組み合わせたバリデーション手法が一般的です。
ソフトウェア使用プロセスのバリデーション
製造に使用するソフトウェア(制御システム、自動検査システムなど)もバリデーションの対象です。QMS省令第5条の6では、品質管理監督システムにおけるソフトウェアのバリデーションを要求しています。主なポイントは:
- ソフトウェアの意図された用途の明確化
- リスクアセスメントに基づくバリデーション範囲の決定
- ユーザー要求仕様(URS)の作成
- 機能試験と性能試験
- 例外処理のテスト
- セキュリティ機能の検証
ソフトウェアバリデーションでは、GAMP 5(Good Automated Manufacturing Practice)などのガイドラインが参考になります。
プロセスバリデーションの実施とモニタリング
サンプルサイズの決定と統計的アプローチ
バリデーションの信頼性を確保するためには、適切なサンプルサイズの決定が重要です。基本的には、統計的手法を用いた科学的根拠に基づくサンプルサイズ設定が求められます:
- 信頼水準と信頼区間の設定: 一般的に95%以上の信頼水準が推奨されます
- 統計的サンプリング計画: ISO 2859(抜取検査)などの規格や検出力を考慮した計画立案
- リスクに基づくアプローチ: 製品のリスククラスや工程の複雑さに応じたサンプルサイズ設定
特に高リスク医療機器の場合、より大きなサンプルサイズと厳格な判定基準が必要となります。
判定基準の設定
バリデーションの判定基準は、明確で測定可能かつ製品品質に直結するものである必要があります:
- 定量的基準の設定: 可能な限り数値で表現された判定基準を設定
- 許容範囲の科学的根拠: 製品仕様や臨床的要求事項に基づく許容範囲の設定
- Critical/Major/Minorの分類: 不適合の重要度に応じた分類と判定基準の設定
判定基準が満たされない場合の対応手順も事前に規定しておくことが重要です。
統計的工程管理(SPC)の活用
バリデーション後のプロセスモニタリングには、統計的工程管理(SPC: Statistical Process Control)の手法が有効です:
- 管理図の活用: X-R管理図、X-s管理図などを用いたプロセス変動の監視
- 工程能力指数の評価: Cp、Cpk、Ppなどの指標によるプロセス能力の定量評価
- トレンド分析: 経時的なデータ分析によるプロセスドリフトの早期検出
SPCは、プロセスの安定性を継続的に確認し、再バリデーションの必要性を判断する上でも重要なツールとなります。
逸脱発生時の対応と再バリデーション
バリデーション済みプロセスに逸脱が発生した場合の対応手順を確立しておくことが重要です:
- 逸脱の分類と評価: 逸脱の重大性評価と製品品質への影響分析
- 是正措置と予防措置(CAPA): 根本原因分析と再発防止策の実施
- 再バリデーションの判断基準: 以下の場合には再バリデーションが必要
- 重大な設備変更・修理
- 材料・部品の重要な変更
- 製造場所の変更
- プロセスパラメータの変更
- 定期的な再バリデーション期限の到来
再バリデーションの範囲は、変更の性質とリスク評価に基づいて決定します。完全な再バリデーションが必要な場合もあれば、部分的な再バリデーションで十分な場合もあります。
実務での活用事例
ここでは、実際の医療機器製造における具体的なプロセスバリデーション事例を紹介します。
射出成形プロセスのバリデーション事例
対象製品: 血液透析用ディスポーザブルチューブコネクタ(クラスIII医療機器)
バリデーションアプローチ:
- IQ段階: 射出成形機の設置環境、電源・水・空気等のユーティリティ、安全機能の確認
- OQ段階:
- 樹脂温度、射出圧力、保持圧力、冷却時間などの主要パラメータの許容範囲確認
- 最悪条件(パラメータ上下限)での成形テスト
- PQ段階:
- 3ロット×各ロット30サンプルの成形(ランダムサンプリング)
- 寸法測定、外観検査、機能試験(接続強度など)の実施
- 長時間連続運転での安定性確認(8時間×3日間)
結果と管理方法:
- 重要パラメータとして樹脂温度、射出圧力、冷却時間を特定
- 各パラメータの許容範囲を確立(例:樹脂温度220±10℃)
- 工程内抜取検査(1時間毎に5個抜取)とSPC管理の導入
- 金型メンテナンスのタイミングを10,000ショット毎に設定
無菌充填プロセスのバリデーション事例
対象製品: 眼内充填用ヒアルロン酸製剤(クラスIV医療機器)
バリデーションアプローチ:
- IQ段階: 充填機の設置確認、クリーンルーム環境の検証、ユーティリティ確認
- OQ段階:
- 充填量精度、充填速度、キャッピングトルクなどのパラメータ確認
- アラーム機能、インターロック機能の検証
- PQ段階:
- メディアフィル試験(培地を用いた無菌性検証)
- 3回の連続製造シミュレーション
- 充填精度、シール完全性、無菌性の検証
結果と管理方法:
- クリティカルパラメータとして充填圧力、HEPA差圧、作業者の無菌操作技術を特定
- 毎バッチの環境モニタリング(浮遊粒子、落下菌)の導入
- 定期的なメディアフィル試験の実施(半年毎)
- 作業者の無菌操作技術の定期トレーニングと評価
PMDAによる査察指摘事例と対応策
指摘事例1: 「プロセスバリデーションの判定基準が製品仕様と整合していない」
背景: 血液回路の接着工程バリデーションで、接着強度の判定基準が製品仕様書の要求値よりも低く設定されていた。
対応策:
- 製品仕様書と整合した判定基準に修正
- 過去のバッチの再評価実施
- 全てのバリデーション計画書と製品仕様の整合性レビュー体制の構築
指摘事例2: 「製造設備の重要な変更後に適切な再バリデーションが実施されていない」
背景: 超音波溶着機のホーンを交換後、部分的な検証のみで完全な再バリデーションが実施されていなかった。
対応策:
- 完全な再バリデーション(IQ/OQ/PQ)を即時実施
- 変更管理手順の見直し(変更レベル分類と必要なバリデーション範囲の明確化)
- 設備変更と再バリデーション要件をリンクさせたマトリックスの作成
プロセスバリデーションの課題と解決策
プロセスバリデーションの実施に際しては、様々な課題に直面することがあります。ここでは典型的な課題と実践的な解決策を紹介します。
リソース不足への対応
課題: バリデーションには人員、時間、予算などのリソースが大量に必要となりますが、多くの企業ではこれらのリソースが限られています。
解決策:
- リスクベースアプローチの導入: 製品リスクと工程の複雑さに基づいて、バリデーションの優先順位と範囲を設定
- 効率的な計画立案: 複数の製品・工程のバリデーションを同時並行で計画
- テンプレートの活用: バリデーション文書のテンプレート化による効率向上
- 段階的実施: 最もクリティカルな工程から順次バリデーションを実施
複雑なプロセスのバリデーション方法
課題: 多数のパラメータが相互に影響する複雑なプロセスでは、全ての条件組み合わせの検証が現実的に不可能な場合があります。
解決策:
- 実験計画法(DOE: Design of Experiments)の活用: 効率的に重要パラメータとその交互作用を特定
- FMEA(Failure Mode and Effect Analysis)の適用: 重要な失敗モードと影響を特定し、検証計画に反映
- 最悪条件(Worst Case)アプローチ: 最も厳しい条件の組み合わせでの検証
- プロセスシミュレーションの活用: コンピュータシミュレーションによる事前検証
サプライヤープロセスのバリデーション管理
課題: 重要な部品・材料の製造プロセスは委託先で実施されることが多く、そのバリデーション管理が課題となります。
解決策:
- サプライヤー品質契約の締結: バリデーション要件を含む品質契約の締結
- サプライヤー監査プログラムの確立: 定期的なサプライヤー監査によるバリデーション状況の確認
- 重要パラメータの特定と監視: サプライヤープロセスの重要パラメータを特定し、定期的なモニタリングを要求
- サプライヤーバリデーション文書のレビュー: 重要な工程のバリデーション文書をサプライヤーから取得してレビュー
製品ライフサイクルにおけるバリデーション維持
課題: バリデーション済みプロセスの長期間にわたる管理と、適切なタイミングでの再バリデーションが課題となります。
解決策:
- 定期的なプロセスレビュー: 6ヶ月〜1年ごとのプロセス性能レビューの実施
- トレンド分析の活用: 工程内検査データや不適合データのモニタリングとトレンド分析による早期問題検出
- 変更管理との連携: 設備、材料、方法、環境の変更と再バリデーション要件の明確なリンク
- 再バリデーション計画の策定: 製品・工程ごとの再バリデーション頻度と範囲の事前計画
まとめと実践のためのチェックリスト
プロセスバリデーションは医療機器の品質保証における重要な要素であり、QMS省令やISO 13485などの規制要件を満たすために必須です。適切に実施されたプロセスバリデーションは、製品品質の一貫性確保、市場での不具合低減、規制遵守の確保につながります。
プロセスバリデーション実施のためのチェックリスト
以下のチェックリストを活用して、自社のプロセスバリデーション活動を評価してください:
計画段階
□ バリデーション対象プロセスの特定と文書化
□ バリデーションの種類(予測的、同時的、回顧的)の決定
□ バリデーションチームの編成(品質、生産技術、製造など)
□ バリデーション計画書の作成と承認
□ 判定基準の明確化と製品仕様との整合性確認
実施段階
□ IQ実施:設備の適切な設置確認
□ OQ実施:パラメータ範囲内での適切な動作確認
□ PQ実施:実生産条件での一貫性確認
□ サンプルサイズの科学的根拠の確認
□ 逸脱発生時の適切な対応と文書化
評価・維持段階
□ バリデーション結果の総合的評価と報告書作成
□ バリデーション文書の適切な保管
□ プロセスの定期的なモニタリングと評価
□ 設計開発文書との連携
□ 変更管理との連携
□ 再バリデーション条件と頻度の設定
今後の規制動向と対応の方向性
プロセスバリデーションに関する規制要件は、技術の進化と共に変化しています。今後の動向として以下が予想されます:
- リアルタイムモニタリング技術の活用: Industry 4.0の進展に伴い、製造プロセスのリアルタイムモニタリングと自動制御が重視される傾向
- データ完全性(Data Integrity)の重要性: 電子記録システムにおけるデータ完全性確保の要求強化
- リスクアプローチの拡大: より効率的なバリデーションのためのリスクアプローチの採用拡大
- グローバル調和の促進: IMDRF(International Medical Device Regulators Forum)を中心としたバリデーション要件の国際調和
医療機器メーカーは、これらの動向を注視し、自社のプロセスバリデーション体制を継続的に改善していくことが重要です。特に、デジタル技術の活用による効率化と、リアルタイムデータに基づく継続的プロセス検証(Continuous Process Verification)への移行を検討することが推奨されます。
適切なプロセスバリデーションの実施と維持は、医療機器の品質確保における基盤であり、患者安全と規制遵守を確実にするための不可欠な活動です。本記事が皆様のプロセスバリデーション活動の改善に役立つことを願っています。


%20(2)-min.webp)