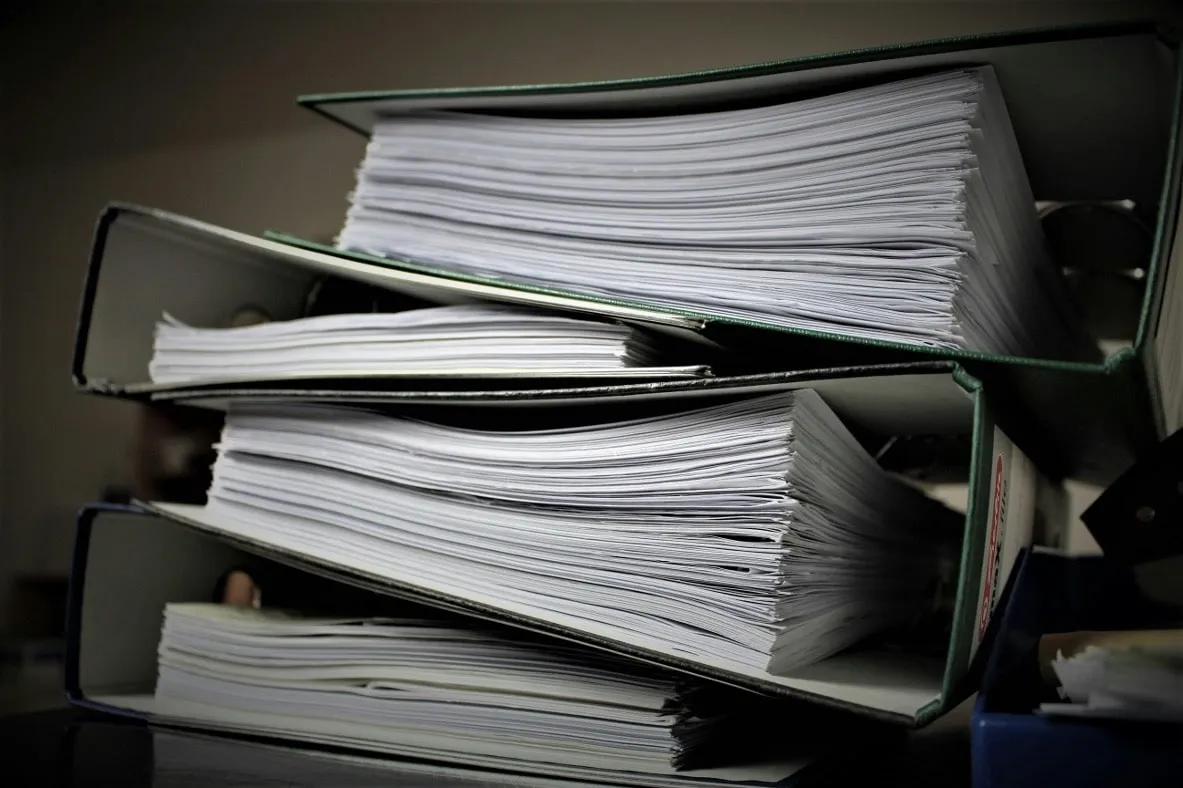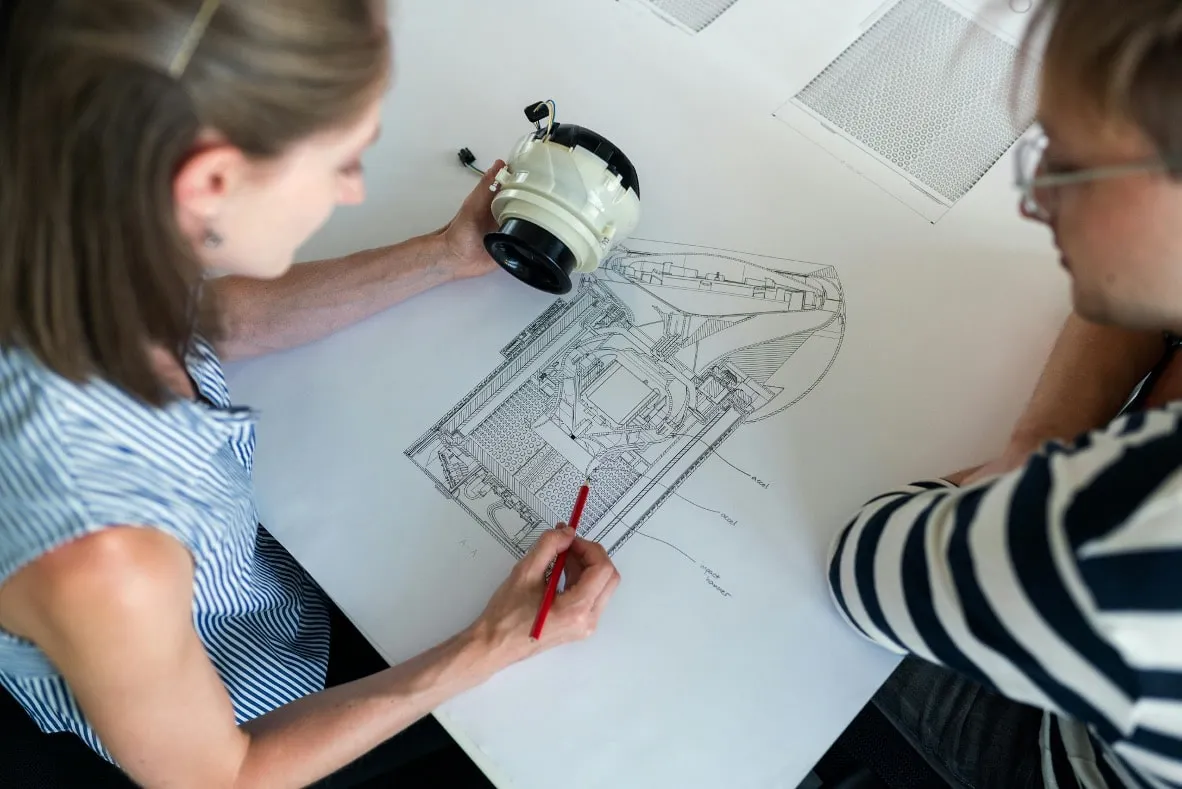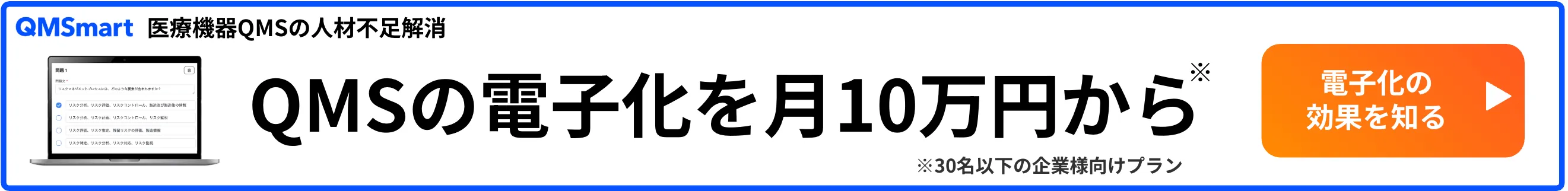はじめに:医療機器QMSにおけるソフトウェアバリデーションの重要性
医療機器業界において、QMS(品質マネジメントシステム)の中でソフトウェアの利用は不可欠なものとなっています。設計開発から製造、品質管理、市販後監視に至るまで、様々なプロセスでコンピュータシステムやソフトウェアが活用されています。これらのソフトウェアが適切に機能していることを保証するため、ソフトウェアバリデーション(妥当性確認)は極めて重要な活動です。
特に近年、電子記録・電子署名の普及に伴い、2005年に発出された「ER/ES指針」(医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について)への対応が改めて注目されています。さらに、クラウドベースのソリューション採用増加やリモートワークの浸透により、電子的な品質管理システムの重要性はこれまで以上に高まっています。
本稿では、医療機器QMSにおけるソフトウェアバリデーションの実践的アプローチを、ER/ES指針との整合性を含めて解説します。規制要件を満たしながらも、効率的かつ実効性のあるバリデーション活動を実現するための具体的な方法論を提供します。
ソフトウェアバリデーションの法的要件と規制背景
QMS省令におけるソフトウェア関連要求事項
医療機器のソフトウェアバリデーションは、QMS省令において明確に要求されています。特に重要な条項は以下の通りです:
第5条の6(ソフトウェアの使用)
1. 製造販売業者等は、品質管理監督システムにソフトウェアを使用する場合においては、当該ソフトウェアの適用に係るバリデーションについて手順を文書化しなければならない。
2. 製造販売業者等は、前項のソフトウェアを品質管理監督システムに初めて使用するとき及び当該ソフトウェア又はその適用を変更するときは、あらかじめ、バリデーションを行わなければならない。(以下略)
第45条(製造工程等のバリデーション)では製造およびサービスの提供にソフトウェアを使用する場合のバリデーション要件が、第53条(設備及び器具の管理)では監視および測定のためのソフトウェアのバリデーション要件が規定されています。
注目すべきは、ソフトウェアバリデーションの要求が単に実施を求めるだけでなく、リスクに応じたアプローチを求めている点です。第5条の6第3項では「品質管理監督システムへのソフトウェアの使用に伴うリスク(当該ソフトウェアの使用が製品に係る医療機器等の機能、性能及び安全性に及ぼす影響を含む)に応じて、バリデーションを行わなければならない」と規定されています。
ISO 13485:2016の関連要求事項
国際規格であるISO 13485:2016においても、QMS省令と同様のソフトウェアバリデーション要件が規定されています。特に以下の条項が関連します:
- 4.1.6:QMSに使用されるソフトウェアのバリデーション
- 7.5.6:製造工程等に使用されるソフトウェアのバリデーション
- 7.6:監視および測定のためのソフトウェアのバリデーション
ER/ES指針の概要と医療機器QMSへの適用
ER/ES指針(薬食発第0401022号、2005年4月1日)は、薬機法の適用範囲内で、電磁的記録や電子署名を使用する際の最低限の要件を規定しています。この指針は医薬品のみならず、医療機器の品質管理にも適用されます。
ER/ES指針の基本的要求事項は以下の3つの柱からなります:
- 真正性(Authenticity)の確保:電磁的記録が完全、正確であり、権限のない変更から保護されていること
- 見読性(Readability)の確保:電磁的記録が人間にとって読める形式で利用可能であること
- 保存性(Storability)の確保:電磁的記録が要求される期間、検索可能な状態で保存されること
さらに、電子署名を使用する場合には、署名者を一意に識別でき、署名日時や意味が明示され、署名後に記録と署名の関係が保持されることなどが求められます。
国際的な規制動向との整合性
FDA 21 CFR Part 11(米国)やEU GMP Annex 11(欧州)など、国際的な電子記録・電子署名に関する規制との整合性も重要です。ER/ES指針はFDA Part 11と基本的に同等の内容ですが、ER/ES指針は紙の記録であっても、その署名が電子的に行われている場合は適用となりますので、実務上は両者の違いにも注意が必要です。国際的な製品展開を行う企業は、各地域の規制要件を統合的に満たすアプローチが求められます。