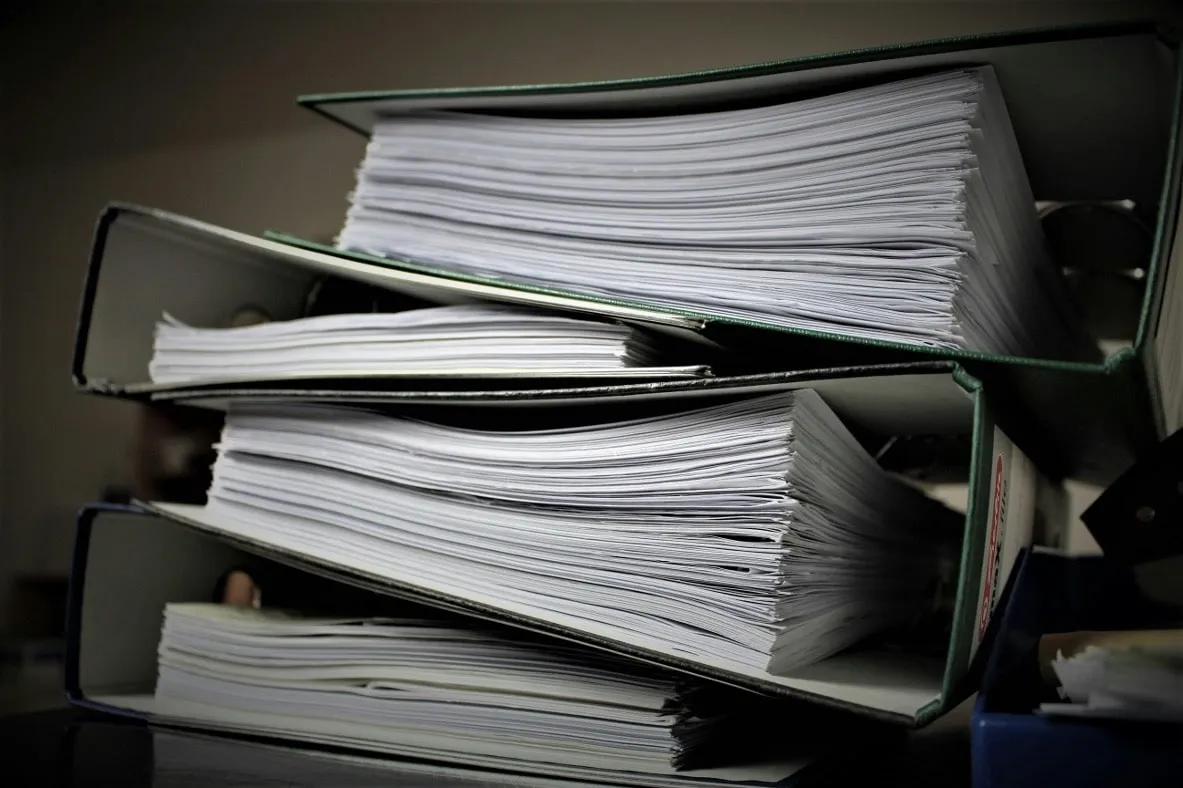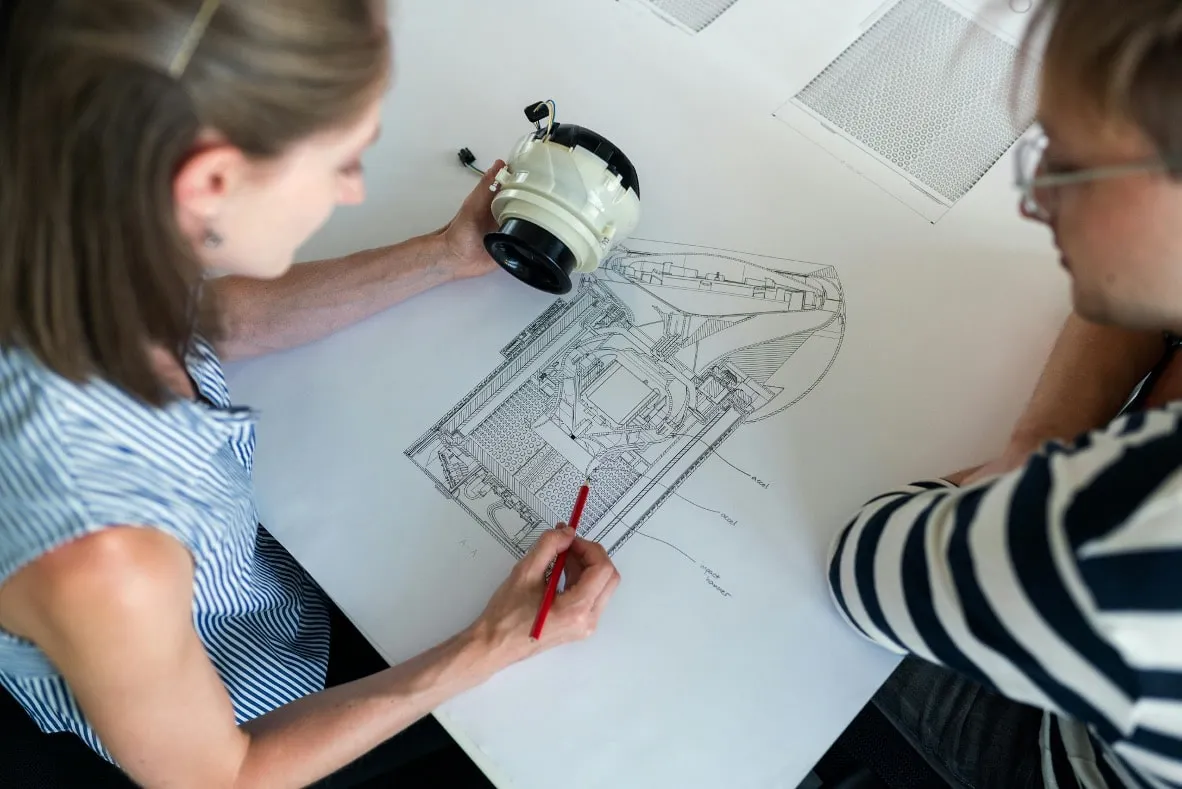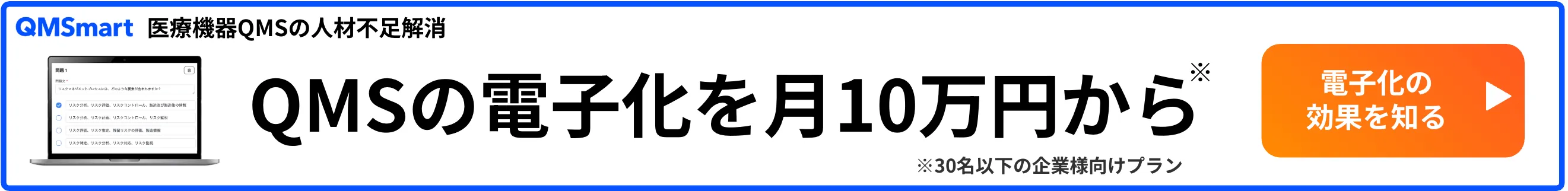はじめに
医療機器のISO13485審査(QMS調査)において、数多くの企業の審査に携わってきた経験から、指摘が多い項目Top 10とその対策についてお話しします。19年間の主任審査員としての経験を通じて、特に指摘が多かった項目に焦点を当て、実践的な改善のポイントをご紹介します。
指摘が多かった項目及び指摘内容は、あくまでも筆者の審査経験からということを、おことわりしておきます。
第1回目は、Top1~3で、第2回目は、Top 4~6でしたが、第3回目は、Top7~9について説明します。
Top7~Top9は次の3項目です。
- Top7:ISO 13485/4.2.4 文書管理(第八条 品質管理監督文書の管理)
- Top8:ISO 13485/4.2.5 記録の管理(第九条 記録の管理)
- Top9:ISO 13485/7.4.2 購買情報(第三十八条 購買情報)
No.7:ISO 13485/4.2.4 文書管理 (第八条 品質管理監督文書の管理)
規格は、必要な文書を要求する場合、「・・の手順を文書化する。」という表現を取っています、これは、原文のThe organization shall document procedure for ・・・・からきています。
この要求文がある場合、手順を文書化する、すなわち手順書を作成しなければなりません。
単に文書化を要求している箇所もあります、単に文書化することが要求されている具体例として、規格は、5.5.1 責任及び権限で、責任及び権限が定められ、文書化されていることを要求しています。また7.3.2 設計開発の開発では、e)で、設計・開発へのインプットに対する設計・開発アウトプットのトレーサビリティを確実にする方法の文書化を要求しています。
なお。記録様式も文書に該当しますので、この文書管理の対象となります。
この手順の文書化は、品質マニュアルの中に含める事もできます。
その根拠は、4.2.2 品質マニュアルの冒頭文及びb)です。「品質マニュアルは、文書化された手順を含む」と読み取れます。
多くの組織は、品質マニュアルの外に規定類や手順書を作成していますが、短い手順でしたら、品質マニュアルに含める事を推奨します。その方がQMS全体の文書体系がシンプルになります。
品質マニュアルに文書化された手順を含める場合、どの部分が、文書化された手順であるか明確にしておく必要があります。
筆者は、ほとんどの文書化された手順を品質マニュアル中に含めて、ISO 13485の認証を取得した組織を知っています。
指摘事項の具体例
(1) 製造部門で作成した手順書を発行する前に、レビューがされず、承認もされていない。
要求:4.2.4 品質マネジメントシステムで必要とされる文書は管理する。a)発行前に適切かどうかの観点から文書をレビューし承認する。
逸脱(不適合):不適合報告書に係る不適合対応として、製造部門で新たに作成された手順書が、適切かどうかの観点からレビューされず、承認されていない状態で発行、そして使用されていた。
(2)製造現場で手順が改善されているにも関わらず、手順書が変更されていない
要求:品質マネジメントシステムで必要とする文書は管理する。b) 文書をレビューする。また必要に応じて更新し、再承認する。
逸脱(不適合):ある部品の製造プロセスは、品質標準書/製品標準書に基づいて製造されることになっています。当該製造プロセスにおいて、表面処理方法、そして材料の購入先が変更されていました。しかしながら、当該変更が品質標準書/製品標準書へ反映されておらず、適切に更新、再承認されていませんでした。
(3)文書変更の場合、規定された部門によって、レビューがされておらず、承認もされていなかった。(又は片方のみの実施)
要求:組織は、その決定の基礎となる関連する背景情報を入手できる立場にある最初に承認した部署、またはその他の指定された部署が、文書の変更をレビューし承認することを確実にする。
逸脱(不適合):製造現場で使用する手順書内のある値(例えば、トルク管理)の管理値が製造部門によって、変更されていた。しかしながら、その管理値の変更が、規格で要求している承認すべき部門(例えば技術部門)にてレビューされておらず、承認されていなかった。
(4)廃止文書の保管期間が省令169号(第3章)第67条の要求を満たしていない
要求:省令169号 第67条(品質管理監督文書の保管期限)・・・特定保守管理医療機器以外の医療機器等に係る製品にあっては、5年間(当該製品の有効期間に1年を加算した期間が5年より長い場合にあっては、当該有効期間に1年を加算した期間)
逸脱(不適合):有効期限が10年の製品がありましたが、廃止文書・期限が5年となっていました。
逸脱(不適合)原因とその対策
(1)製造部門で作成した手順書を発行する前に、レビューがされず、承認もされていませんでした。
原因として、製造部門で作成された手順書に対し、レビュー及び承認部門が明確でないことがあげられる。
文書管理規定が、製造部門で使用する手順書に及ぶことを製造部門が理解していないことも原因となる場合もある。
製造工程管理規定など、製造部門がよく使用する管理規定などで、製造部門が独自に作成する手順書について、レビューと承認の規定を明記しておくことなどが対策としてあげられます。教育訓練も再発防止として、有効と考えられます。
(2)製造現場で手順が改善されているにも関わらず、手順書が変更されていない
製造部門で製造工程を変更するプロセス、手順が明確でないことが、原因としてあげられます。
更に言えば、表面処理方法の変更が、設計変更ととらえる意識が薄かったなどもあげられます。
これらの問題の根底には「製造部門と設計部門の認識のずれ」があり、その背景として以下の要因が考えられます。
- 役割分担の曖昧さ: 製造部門が「現場改善」と「設計変更」の境界を理解していない
- プロセスの不明確さ: 製造工程変更時の正式な承認プロセスが確立されていない
- 文書管理意識の格差: 設計部門は文書管理意識が高いが、製造部門は低い
- 口頭で済ませる慣習: 長い取引関係により書面化を怠る傾向
製造工程の変更も設計変更の一部でありえることを明確にして、品質標準書/製品標準書に反映すべき内容を明確にすることが再発防止につながると考えられます。
(3)文書変更の場合、規定された部門によって、レビューがされず、承認もされていなかった。(又は片方のみの実施)
製造部が、製造プロセスを変更する際の明確な手順が無かったことが原因としてあげられる。
製造部門が責任を持って変更できる範囲と、他部門(例え技術部門)のレビュー、承認が必要な範囲の切り分けが明確でなかったことも原因としてあげられる。
(4)廃止文書の保管期間が省令169号(第3章)第67条の要求を満たしていない
原因として、ISO 13485の要求事項のみを適用する場合があります。さらに、登録製造所が海外の場合、製品ごとの有効期間を正確に把握していなかったのが原因として挙げられます。
QMS調査(省令169号調査)において、海外の登録製造所の文書管理規定が、この省令169号(第3章)第67条の要求を満たしていないケースが多く見受けられますが、その原因として、国内製造販売業者が、海外の登録製造所に対し、省令169号(第3章)第67条の要求を正確かつ明確に伝えていない点があります。
重要なポイント
逸脱(不適合)の(1)~(3)は、いずれも製造部門にて作成した場合の文書についてです。設計部門、品質管理部門及び品質保証部門などは、文書管理の意識が高く、文書管理の要求に自然に従っている場合がありますが、製造部門は文書管理の範囲にはいるという意識が低く、なんらかの理由で製造工程の変更が必要な場合、必要に迫られて手順の変更は行うが、文書管理の規定に従わないというケースがほとんどです。
逸脱(不適合)の(1)~(3)の再発防止は共通点が多いため、これらを確実に対策することが重要です。
逸脱(不適合)(4)については、特に登録製造所が海外の場合が多く見受けられます。この対策としては、輸入製品ごとの有効期間を登録製造所との間ではっきりさせることが、まず実施すべきことと考えられます。
No.8:ISO 13485/4.2.5 記録の管理(第九条 記録の管理)
文書と記録の定義は、ISO 9000:2015によれば、下記です。
3.8.5 文書
情報及びそれらが含まれている媒体
3.8.10 記録
達成した結果を記述した、又は実施した活動の証拠を提供する文書(3.8.5)
定義によれば、記録は文書に含まれているが、ISO 13485では、文書管理と記録の管理とを分けています。
ISO 13485:2016/4.2.4 文書管理の冒頭には、下記の記載があります。
品質マネジメントシステムで必要とされる文書は管理する。ただし,記録は文書の一種ではあるが,4.2.5に規定する要求事項に従って管理する。
指摘事項の具体例
(1)電子ファイルによる記録について、手順が文書化されていない。
要求:組織は、記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定するために、手順を文書化する。
逸脱(不適合):紙に記録する場合の規定はされていましたが、電子ファイルについての記録の識別、保管、セキュリティ及び完全性の維持、検索、並びに保管期間及び廃棄に関しての手順が文書化されていませんでした。
(2)記録の保管期間が省令169号(第3章)第67条の要求を満たしていない
要求:特定保守管理医療機器以外では、当該製品の有効期間に1年を加算した期間が5年より長い場合にあっては、当該有効期間に1年を加算した期間、記録を保管すること
(著者コメント)まずなぜ製品の有効期間まで記録を保存しなければならないかですが、製品を出荷した後に、有効期限内の使用中に製品が不具合などを生じた場合、不具合原因を究明するために、その製品の製造記録などを調査する必要があります。そのため、製品の有効期間中には、その記録を保存する必要が生じます。では、なぜプラス1年とするか、製品の有効期間は通常製品の出荷時点からカウントされる場合があります。しかし製造記録を取った時点から、出荷時点までは、製造期間+製品在庫期間が生じます。そのため有効期間にプラス1年と定められているのではないかと考えられます。
ただ、省令169号では、有効期間+1年が5年未満の場合、最低でも5年間保存することを要求しています。
逸脱(不適合):保管期間が「製品有効期間+1年」に規定されていなかった。
例:製品寿命(又は有効期間)は 7年ですので、8年の保管期間が必要です。しかしながら、品質記録一覧表には、保管期間5年と規定された記録が複数ありました。
(3)機密健康情報を保護するための方法が規定されていない
要求:組織は、適用される規制要求事項に従い、記録に含まれる機密健康情報を保護するための方法を規定し、実施する。
逸脱(不適合):記録に含まれる機密健康情報を保護するための方法が規定されていませんでした。
逸脱(不適合)原因とその対策
(1)電子ファイルによる記録について、手順が文書化されていない。
紙への記録については、手順が文書化されていますが、世の中の流れにしたがって、記録は現在、パソコンやサーバーに保管されることが一般的です。これらの電子記録には、紙とは異なる管理が必要になります。
しかしながらそれら電子記録に対して、手順を文書化しなければならないというところまで、考えが及ばなかったことが原因として挙げられます。
対策としては、電子化された記録に対して、紙とは異なる点に着目して手順を文書化することです。
規格の要求は、「記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄に関して手順化する。」です。特に保護について、データ消失リスクに備えて、バックアップを手順に加えておくことが大事です。
(2)記録の保管期間が省令169号(第3章)第68条の要求を満たしていない
この原因と対策は、文書管理の項で、述べたことと同様です。
原因として、ISO 13485の要求事項のみを適用する場合があります。さらに、登録製造所が海外の場合、製品ごとの有効期間を正確に把握していなかったのが原因として挙げられます。
QMS調査(省令169号調査)において、海外の登録製造所の文書管理規定が、この省令169号(第3章)第68条の要求を満たしていないケースが多く見受けられますが、その原因として、国内製造販売業者が、海外の登録製造所に対し、省令169号(第3章)第68条の要求を正確かつ明確に伝えていない点があります。
再発防止としては、輸入製品ごとの有効期間を登録製造所との間ではっきりさせることが、まず実施すべきことと考えられます。
(3)機密健康情報を保護するための方法が規定されていない
この「機密健康情報を保護するための方法を規定すること」は、ISO 13485が、2003年版から2016年版に改訂されるときに、追加された要求事項です。そのための見落としも一因と考えられます。
品質マニュアルには、ISO 13485の:2016版の要求どおり「組織は、適用される規制要求事項に従い、記録に含まれる機密健康情報を保護するための方法を規定し、実施する。」と記載しておきながら、その下位文書である手順書に、“記録に含まれる機密健康情報を保護するための方法” を規定していなかったのがその一例です。
文書管理と記録の管理の手順書を一緒にして、文書記録管理手順書としている場合、記録の管理手順が分かりにくいというのも、その逸脱(不適合)原因となるかも知れません。
対策としては、ISO 13485の:2016版を忠実にしたがって、文書化、規定する事を求めている箇所を明確にして、その要求を手順書に漏れなく、含める事などでしょう。
重要なポイント
記録が電子化されている場合の記録の管理については、紙に記録する場合と管理方法が異なりますので、電子化された記録に合うような手順を文書化する必要があります。
規格の要求「記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄」のうち、特に電子記録の保護に関しての管理は紙記録の場合の管理と異なります。サーバー内に保管された電子記録は、その故障に備えて他の記憶装置にバックアップすることなどが求められます。一般的に組織の情報部門などがその管理にあたっていて、ISO 13485の認証範囲の組織外である場合には、手順書にどう盛り込むか注意が必要です。
機密健康情報を保護するための方法については、組織に入ってくる機密健康情報の特定とその情報が最初に入ってくる部門を特定することがまず必要です。
その上で、その情報が組織内に流れる事のないような工夫が必要です。
例えば、医療機器に不具合が生じた場合に、患者個人情報を含んだ機密健康情報が組織内に流れてきた場合、その患者個人情報を最初に入手した部門が削除、黒塗り、または抽象化表現にすべきでしょう。
また、機密健康情報を含んだ情報が紙であった場合は、組織内に流れないように鍵のかかるロッカーなどに保管することなどが考えられます。
No.9:ISO 13485/7.4.2 購買情報(第三十八条 購買情報)
購買情報とは、供給者へある製品、ある部品またはある材料を発注する際に、供給者へその発注品に対して要求する情報のことです。
この情報を明確にしておかないと、後々問題になります。
例えば、自社の要求と異なる部品が納入されてきた場合でも、その異なることを主張すべき証拠文書(購買情報を記載した文書)がないために、供給者と揉めることになります。
ISO 9000:2015では、製品の定義は下記となっています。
3.7.6 製品・・組織と顧客との間の処理・行為なしに生み出され得る、組織のアウトプット。
Output of an organization that can be produced without any transaction taking place between the organization and the customer.
規格 ISO 13485において、購入する物、供給者の提供物は、材料、部品、設備でも、“製品”と表現されます。
指摘事項の具体例
(1)発注した製品の製品仕様が文書化されていない、または不十分
要求:購買情報 には、購買する製品を記述又は参照 し、適切 な場合、次を含める。a)製品仕様
逸脱(不適合):
事例1)医療機器A用の購入部品について製品仕様が明確ではありませんでした。
※注)製品仕様;性能値、図面、回路図、他
事例2)メイン基板の供給者には、実質検査を要求していますが、製品仕様として提出された資料には、検査の要求記載がありませんでした。
(2)供給者が製品の製造工程を変更する場合の、事前承認契約がない
要求:購買情報には、適用される場合、購買製品が規定された購買要求事項を満たす能力に影響がある全ての変更について、購買製品への変更を供給者が実施する前に組織に通知することへの書面の合意を含めること。
逸脱(不適合):
事例1)登録製造業者(工程:主たる組立)であるA社とは取決めは締結されています。しかし、取決めには購買物品等要求事項への適合性に影響を及ぼす変更をA社から製造販売業者に通知することが含められていませんでした。
事例2)供給業者Bとの購買情報の中に、購買製品が規定された購買要求事項を満たす能力に影響がある全ての変更について、供給者が購買製品への変更を実施する前に組織に通知することへの書面の合意が含まれていませんでした。
逸脱(不適合)原因とその対策
(1)発注した製品の製品仕様が文書化されていない、または不十分
原因の一例:メイン基板の設計開発を供給者と購入者の双方の合意に基づいて行った。また、品質検査成績書の提出を口頭で求めた結果、品質検査成績書が提出されたため、書面での取り交わしを行っていなかった。
この供給者へ渡すまたは提示する製品仕様が不十分な事例の原因は、組織(発注者)と供給者との間に長い取引関係があって、組織側と供給者との間に、打ち合わせなどで取り決めてしまって、書面(文書)にしていない例が多い様です。そしてその製品仕様は、供給側はなんらかの形で文書化して、保存/維持しています。供給者側はそれがないと製造できないためです。
ISO 13485審査で不適合を受けた事により、供給者から製品仕様を入手するという逆転現象が起こることも、珍しくありません。
対策としては、妙案はありませんが、購買部門がしっかりすることが基本のようです。例えば供給者から提出された見積書の詳細内訳と製品仕様書を突き合わせて、内容に齟齬が無いか確認することなどです。
また、自社で製品仕様・購入仕様書を完成できないようなケースでは、供給者に納入仕様書を作成して貰って、それを承認することで、製品仕様書とすることなどが考えられます。
(2)供給者が製品の製造工程を変更する場合の、事前承認契約がない
原因の例:
例1)合意書締結当時には、法に従った合意内容であった。 しかし2016年のISO 13485 規格改定により製造業者からの事前連絡が必要となったが、それに即した合意書の変更が行われなかった。
例2)供給者に製造を依頼する際、製造手順を指示していた。そのため、当該取決めを文書にて合意する必要がないと判断していた。
規格は、“適用できる場合、購買製品が規定された購買要求事項を満たす能力に影響がある全ての変更について”とされているので、すべての購入製品について適用される訳ではありません。購入製品仕様書に記載内容だけでは書き表せなく、供給業者の製造工程を変更すると組織の製造する最終製品に影響を及ぼすような購入製品に対して要求することを意図しています。
したがって、そのような購入製品はどれが該当するか選別し、工程変更が生じたら、どういう影響があるかのリスクを検討してみることも対策の一つになると考えられます。
製造工程の変更要素は、一般的に「4M」と呼ばれ、「Man(人)」「Machine(機械)」「Material(材料)」「Method(方法)」の4つの要素の変更を指します。これら4つの要素の変更は、製品の品質や生産性に影響を及ぼすため、変更管理が重要になります。
重要なポイント
(1) 購入製品仕様の文書化
上にも述べたように、供給者と長い付き合いの中で、発注する側の組織が購入製品仕様を文書化または不十分な場合が見受けられます。例えば、ある購入製品をなんからの事情(海外進出又は供給者が廃業など)で、他の供給者に発注する場合に、困る事になります。
購入製品仕様書が十分かどうかチェックする方法としては、現在継続発注している供給先以外に発注することを考えてそれが可能であるか、検討することも一方法でしょう。
購入製品仕様書が自社で作成するのが、困難な場合には供給者から詳細かつ正確な納入仕様書を入手するのも一方法です。
発注行為は、金が絡む契約行為です。もし、自社にとって不都合な製品が入ってきたとして、返品できるかどうかは、その組織が管理する購入製品仕様の内容次第です。購入製品仕様に合う製品でしたら、返品はできないことになります。
(2) 供給者が製品の製造工程を変更する場合の、事前承認契約
規格は、“適用できる場合、購買製品が規定された購買要求事項を満たす能力に影響がある全ての変更について”とされているので、すべての購入製品について適用される訳ではありません。
モーター、リレー又はLEDなどで、メーカーの標準品で、製品仕様を満足していれば、購入側の組織の最終医療機器の仕様・性能に影響を与えないとしたら、製造工程変更の事前連絡/承認は不要でしょう。標準電気部品などで、カタログなどで、「予告なく変更することがある」と明記されている製品もあります。
“適用できる場合、購買製品が規定された購買要求事項を満たす能力に影響がある全ての変更について”が適用できるのは、購入製品仕様書または納入仕様書で書ききれない要素がある場合です。
例えば摩擦、摺動性、色味、衝撃性能などは、購入製品仕様書または納入仕様書で記載しきれない場合があります。
筆者が経験した事例をお話しします。医療機器を支えるキャスターを病院内で設置するときに、ちょっとした段を乗り越えるときに、あるロットから破損する事故が多発した。
供給者と良く打ち合わせると樹脂成型工程で、ランナーやゲートを再利用するために粉砕され、原料の投入比率が変更された事が分かった。材料そのものの変更はないため、仕様書からは逸脱しない。
これは、「購入製品仕様書または納入仕様書では記載しきれてなかった。」事例です。
(注)
樹脂成形において、製品にくっついてくる部分を一般的に「ランナー」または「ゲート」と呼びます。ランナーは樹脂が金型に流し込まれるための通路で、ゲートはランナーから製品に樹脂が流し込まれる部分のことです。
これらのランナーやゲートは、成形後、製品から切り離されます。切り離されたランナーやゲートは、再利用するために粉砕され、原料として再投入される場合があります。

-min.webp)